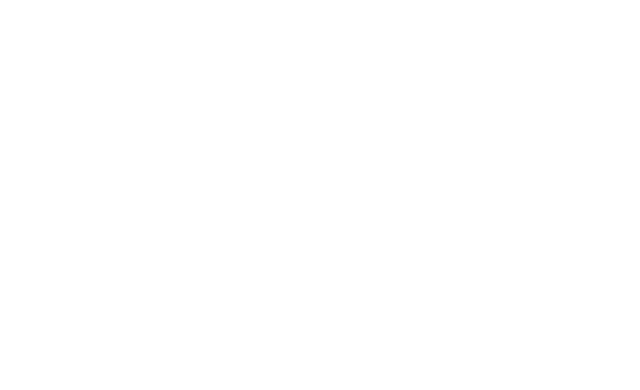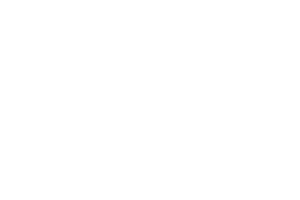目次
-
- 1. アルバイト先のハラスメントとは?7種類を紹介
- 2. アルバイト先でハラスメントを受けたときの対処法
- 3. ハラスメントに遭いにくい職場を探すコツ
- 4. ハラスメントに関するよくある質問
- Q.ハラスメントを受けていて職場に行きたくありません。バイトを休んでもいいですか?
- Q.学生でアルバイトをしていますが、バイト先の店長からパワハラを受けています。店長以外に社員がいないので相談できる大人がいなくて困っています。
- Q.アルバイトで毎回ほぼ必ず残業が発生するのですがハラスメントになりますか?
- Q.アルバイト先で誰にハラスメントを受けたかによって、対処法は変わるのでしょうか? 対処法の違いがあれば教えてください。
- Q.バイトでパワハラを受けたことに対して、どの程度の被害なら損害賠償を請求できますか?
- 5. 監修者からのアドバイス
- 6. まとめ
アルバイト先でパワハラやセクハラなど、嫌な思いをしたことはありませんか? もし職場で不適切な言動を受けたら、どうすればいいのでしょうか? この記事では、キャリアアドバイザーの谷所さん監修のもと、アルバイト先でのハラスメントの事例やその対処法、相談窓口などを紹介します。自分の権利を守るため、そして安心して働ける環境を確保するための参考にしてみてください。
1.アルバイト先のハラスメントとは?7種類を紹介

ハラスメント(harassment)とは「嫌がらせ」という意味で、人に不快感を与える行為全般を指します。ハラスメントには一定の判断指標はありますが、行った側が嫌がらせをしようと思っていなくても、受け取る側が不快に感じた場合はハラスメントに該当する点に注意が必要です。
以下では、アルバイト先の職場で問題となる、代表的な7つのハラスメントについて解説します。
パワーハラスメント(パワハラ)
パワーハラスメント(以下、パワハラ)は、同じ職場の上司や先輩などが自分の立場や人間関係を利用して、仕事に関係ないことで無理をさせたり、心や体に苦痛を与えたりして職場の雰囲気を悪くすることを指します。パワハラは大きく以下の6つに分類され、それぞれの事例もあわせて紹介します。
- 身体的な攻撃……暴行、障害
- 精神的な攻撃……脅迫、侮辱、ひどい暴言
- 過大な要求……業務に不要なことや明らかにできないことの強制
- 過小な要求……能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を与えられる、仕事を与えない
- 人間関係からの切り離し……仲間はずれ、無視
- 個の侵害……プライベートに過度に立ち入る
アルバイトの職場におけるパワハラの事例
【身体的な攻撃】
身体的な攻撃には、殴る、叩く、蹴るなどの身体的な暴行はもちろん、相手に物を投げつける行為なども含まれます。ただし、誤ってぶつかってしまった場合などは、身体的な攻撃に該当しません。
- 仕事でミスをすると、丸めたポスターで頭を叩かれる
- 「仕事の覚えが悪い」と言われ、座っていた椅子の背面を蹴られた
【精神的な攻撃】
必要以上に繰り返し怒る、人格や能力を否定するなどして従業員に対して精神的に負荷をかける行為が精神的な攻撃に該当します。ただし、遅刻や業務上の重大なミスに対する指導の範囲であれば精神的な攻撃には当たりません。
- 他のスタッフもいる前で、「小学生でもできる」「お前を採用したのが失敗だった」と大きな声で怒鳴られた
- 他の従業員も宛先に含めたメールで罵倒された
【過大な要求】
その人のスキルや経験値、仕事量を越えた仕事を押し付けるといった過大な要求もパワハラの一種です。ただし、繁忙期に業務量が増えたり、従業員育成のために難しい業務を任せたりすることは過大な要求にはなりません。
- 「他の人は帰っていいけど、お前はこの仕事が終わるまで帰るな」などと、終業間際にも関わらず、膨大な量の仕事を押しつけられる
- 業務とは関係のない私的な雑用を強制させられる
【過小な要求】
嫌がらせのために本来の仕事を与えないといった過小な要求もパワハラに含まれます。一方、労働者の能力に応じて業務内容や量を調整することは、過小な要求に当たりません。
- コンビニバイトで、他の新人はレジや品出しも任されているのに、自分だけゴミ出しや掃除しかさせてもらえない
- 他のアルバイトは普通に働いているのに、自分が職場に行くと「今日は仕事がないから帰っていいよ」と言われ、明らかに不自然な扱いを受けている
【人間関係からの切り離し】
一人だけ隔離する、無視する、仲間はずれにすることなどが該当します。なお、新しく入社した従業員を育成するために短期間集中して別室にて研修を行うことなどは人間関係の切り離しには当たりません。
- 自分だけ送別会に呼ばれない
- 性的指向・性自認についての噂が広まり、職場で無視されるようになった
【個の侵害】
個の侵害は、従業員のプライベートに必要以上に立ち入ることを指します。例えば、性的指向や性自認、病歴、不妊治療などの個人情報を本人の許可なく暴露することなどが該当することがあります。ただし、労働者への配慮を目的として労働者の家族状況をヒアリングしたり、本人の許可を得たうえで人事労務担当者に情報を共有することなどは、個の侵害に当たりません。
- 社員が従業員の写真を撮影して、私物化している
- 自分の交際相手について、社員からしつこく聞かれる
セクシュアルハラスメント(セクハラ)
セクシュアルハラスメント(以下、セクハラ)は、性的な言動によって不快な思いをすることを指します。職場で嫌がらせのように性的な冗談を言われる、しつこく食事やデートに誘われる、必要のない体の接触をされるなどはセクハラの一例です。性別や役職などに関係なく、どんな人でも被害者・加害者になる可能性があります。そのうえで、セクハラには、大きく分けて「対価型」と「環境型」の2種類があります。
- 対価型:性的な言動を拒否したことにより、解雇・降格・減給などの不当な扱いを受けるケース
- 環境型:性的な言動により職場の居心地が悪くなり、業務に支障をきたすケース
アルバイトの職場におけるセクハラの事例
【対価型】
- 職場内で性的な発言をした上司に改善を求めたところ、給料を下げられた
- 飲み会で社員に対してお酌を強要されたので拒否したところ、「断ったら解雇だ」と脅された
【環境型】
- 社員からスリーサイズや恋人の有無を執拗に聞かれ、その社員に対して恐怖心を抱くようになった
- 恋人がいないだけで事実無根の噂を広められたため、職場の居心地が悪くなって退職を考えている
カスタマーハラスメント(カスハラ)
カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)は、お客さまや取引先からの商品やサービスを改善するための苦情とは異なり、無理な要求や不当に文句をつける悪質なクレームなどを指します。それにより、業務が妨げられる、精神的な負担になるといった悪影響が出ることがあります。
アルバイトの職場におけるカスハラの事例
- お客さまから理不尽な要望が繰り返し寄せられることによって他の業務を行う時間が削られている
- お客さまから「要望に応えないとSNSにお店の悪い口コミを書く」と脅され苦痛を受けている
参考:アルバイト従業員へのカスタマーハラスメント実態調査|マイナビキャリアリサーチLab
モラルハラスメント(モラハラ)
モラルハラスメント(以下、モラハラ)は、モラルに反するような嫌がらせやいじめなどで、働く人の気持ちや尊厳を傷つけたり、心や体にダメージを与えたりすることです。その結果、精神的な健康を損ない、仕事を続けられなくなることもあります。
アルバイトの職場におけるモラハラの事例
- 「お前の声を聞いているとイライラする」「本当に使えないね。何度言ったら分かるの?」などと嫌味を言われ、傷ついた
- 自分に対してわざとらしく舌打ちやため息をされる
マタニティハラスメント(マタハラ)
マタニティハラスメント(以下、マタハラ)は、女性(母親)が妊娠や出産、育児などを理由に、上司や同僚からの不当な対応を受けることです。産前休暇の取得を上司に相談したところ、「休みを取るなら辞めてもらう」と言われるケースは典型的なマタハラです。
アルバイトの職場におけるマタハラの事例
- 「家の事情で休むことが多いから、仕事を教えても無駄だよね」と言われ、仕事を教えてもらえない
- もうすぐ産休に入る予定があり、本来は受験資格のある昇進試験を受けさせてもらえない
パタニティハラスメント(パタハラ)
パタニティハラスメント(以下、パタハラ)とは、男性(父親)が育児休業を取ったり、子育てに関わろうとしたりすることに対して、職場で嫌がらせを受けることを指します。育児休暇取得の妨害や減給、配置転換、心無い発言などはパタハラに当たる可能性があります。
アルバイトの職場におけるパタハラの事例
- 「育児による早退は、正直迷惑だ」「子どもがいるなら、専業主婦(夫)になったら?」と嫌味を言われた
- 「育児が忙しいので出勤頻度を減らしたい」と社員に相談したところ、退職をすすめられた
ケアハラスメント(ケアハラ)
ケアハラスメント(以下、ケアハラ)とは、家族の介護をする従業員が嫌がらせを受けたり、不当な扱いをされたりすることです。介護休暇の取得を認めない、介護を理由にした減給、心無い発言などがケアハラに当たります。
アルバイトの職場におけるパタハラの事例
- 「介護が大変だからって、バイトに迷惑かけないで」とベテランの先輩に言われた
- 「そんなに休むなら、辞めたほうがいいんじゃない?」などと退職を促された
参考:職場におけるハラスメント 対策パンフレット|厚生労働省
確かめようアルバイトの労働条件|厚生労働省
2.アルバイト先でハラスメントを受けたときの対処法

実際にアルバイト先でハラスメントを受けた場合は、どう対処すれば良いのでしょうか。その具体的な対処法を6つ紹介します。現在ハラスメントを受けていない人も、もしものときのために覚えておくと良いでしょう。
ハラスメントを受けた証拠を残す
ハラスメントを会社の相談窓口や公的機関に相談する際には、客観的に事実を証明できる証拠を残すことが重要です。これによって客観的に状況を伝えられます。
【証拠の残し方】
- メモを取る(日時、場所、関係者の氏名、加害者の言動、目撃者の有無を記録)
- 録音・スクリーンショット(発言やメッセージの記録)
- 写真を撮る(暴力による傷などを記録)
- 医師の診断を受けて「診断書」をかいてもらう
家族や友達など信頼できる人に話す
ハラスメントを一人で抱え込むと、精神的に追い込まれてしまうことがありますが、家族や友達、同僚などの信頼できる人に話すことで、アドバイスをもらったり、冷静に状況を整理したりできる可能性があります。また、相談することで解決の糸口を見つけやすくなるでしょう。
話し合いで解決できるか試みる
加害者がハラスメントの自覚がなく言動を行っている場合、当事者同士の話し合いによって改善することもあります。ただし、改善しない場合や、話し合いの場を持とうとすることで状況が悪化しそうな場合は、無理に接触せず、上司や人事など第三者を介するようにしましょう。
カウンセリングを受ける
臨床心理士などの専門家によるカウンセリングを受けることで、問題解決につながる可能性があります。ハラスメントによるストレスや心理的な負担を軽減し、対処する際にも効果的です。
会社の相談窓口を活用する
2020年6月(中小企業は2022年4月)に施行された労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)によって、事業者にはハラスメントの早期発見・対処するために相談窓口を設置することが義務づけられています。そのため、アルバイトでも会社の相談窓口を利用できます。一般的に、総務や人事が窓口になっているため、問い合わせてみましょう。
公的機関に相談する
当事者同士や会社内での解決が難しい場合は、各都道府県に設置している労働相談コーナーなど公的機関に相談することもできます。
【相談窓口の一例】
- 厚生労働省「都道府県労働局」
- 厚生労働省「総合労働相談コーナー」
- 法務省「みんなの人権110番」
法的措置を検討する
ハラスメントが深刻で解決が難しい場合、費用がかかりますが、弁護士などの専門家に相談して、訴訟や調停など法的手続きを検討することも一手です。法的手続きにおいては、録音データやメモなどの証拠が重要な役割を果たします。
ハラスメントを受けたら退職を選ぶことも一つの対処法
ハラスメントの改善の見込みがない場合は、退職を検討することも大切です。無理に働き続けると健康を損なう可能性があるため、自分にとってより良い職場を探すことも選択肢の一つです。
3.ハラスメントに遭いにくい職場を探すコツ

誰もがハラスメントに遭遇する可能性がありますが、できる限り避けたいものです。100%防ぐことは難しいものの、安心して働ける職場を選ぶためのコツを4つ紹介します。
インターネットで口コミを検索する
気になるアルバイト先があれば、インターネットで検索してみましょう。口コミサイトなどで職場の評価を確認したり、SNS上でその職場に関する投稿を探したりするのが有効です。ただし、口コミは個人の主観が含まれるため、すべてを鵜呑みにせず、あくまで参考情報として活用しましょう。
アルバイト先に行って、職場の雰囲気をチェックする
アルバイト先に足を運んで、職場の雰囲気を直接確認するのも一つの方法です。特に飲食店やアパレルショップなどでは客としてその店に訪れて、接客態度、スタッフ同士の関係性、コミュニケーションの取り方といった点に違和感がないか観察すると良いでしょう。職場の雰囲気が良ければ、働きやすい環境である可能性が高いでしょう。
面接で希望する条件や待遇をできるだけ伝える
面接の際に希望する条件や待遇をできるだけ伝えることで、お互いの認識のズレを防ぐことができます。アルバイト先から無理な条件が提示されたら「対応できません」とはっきり断ることも重要です。断った時に面接官の態度が横柄であれば、ハラスメントが発生しやすい可能性があるため注意しましょう。
複数のアルバイト先に応募して比較する
特に初めてアルバイトをする人は、職場のルールや雰囲気が分かりにくいこともあるでしょう。そのため、複数のアルバイト先に応募して比較検討することで、違和感のあるポイントにも気づきやすくなります。比較する際は、従業員同士のコミュニケーションのとり方や上司の態度が高圧的ではないか、職場の雰囲気が明るく風通しが良さそうか、といったポイントをチェックしてみましょう。
4.ハラスメントに関するよくある質問

ハラスメントに関するよくある質問にキャリアアドバイザーがお答えします。
Q.ハラスメントを受けていて職場に行きたくありません。バイトを休んでもいいですか?
ハラスメントを理由に職場に行きたくない場合、休むことも選択肢の一つですが、根本的な解決にはなりにくいためあまりおすすめしません。ただし、精神的に厳しい状況にある場合は、必ずアルバイト先に連絡を入れたうえで休むようにしてください。
ハラスメントの問題を解決するためには、一人で抱え込まずに信頼できる人や相談窓口に相談することが重要です。長期間休むことで職場に行くことへの抵抗感が増すことも考えられるため、できるだけ早く相談して対処しましょう。
Q.学生でアルバイトをしていますが、バイト先の店長からパワハラを受けています。店長以外に社員がいないので相談できる大人がいなくて困っています。
店舗の経営形態によって対処法を考えましょう。チェーン店の場合、会社の本部に相談窓口が設けられていることが多いため、まずは相談窓口に相談してみることをおすすめします。個人経営店の場合は、店長に直接話しかけることも考慮に入れましょう。家族や信頼できる友人に加え、外部の相談窓口を利用することも一つの手段ですが、店長と話す環境が整っていない場合は、退職して新たなアルバイト先を探すことも検討しましょう。
Q.アルバイトで毎回ほぼ必ず残業が発生するのですがハラスメントになりますか?
残業時間が月間45時間を超える場合などは残業時間過多で違法になる可能性はありますが、残業が発生するだけではハラスメントにならないでしょう。ハラスメントに該当する可能性がある例としては、体調不良を理由に残業を断っても認められないケース、社員に残業が難しいことを伝えても改善されないケース、嫌がらせとして残業が発生しているケースがあります。
また、事業者が36協定を締結していない場合や、労働条件通知書や雇用契約書に残業について記載されていない場合は、そもそも従業員に残業を命じることはできません。いずれにしても残業を避けたい場合は、アルバイト先の責任者に相談をしてみましょう。
Q. アルバイト先で誰にハラスメントを受けたかによって、対処法は変わるのでしょうか? 対処法の違いがあれば教えてください。
加害者の立場によってハラスメントの対処法は異なります。以下にその一例を挙げます。
- 店長からハラスメントを受けた場合……本部の相談窓口やエリアマネジャー、外部の相談窓口に相談する
- 社員からハラスメントを受けた場合……店長に相談できる環境が整っているなら、まずは店長に相談する
- 年齢が上のパートタイマーからハラスメントを受けた場合……社員スタッフや店長といった管理者に相談する
- 同年代のアルバイトの同僚からハラスメントを受けた場合……アルバイトを管理している社員スタッフや店長に相談する
基本的には、部署の責任者に相談することが推奨されます。店舗の店長や社員だけでなく、アルバイト先の会社の人事や総務、外部の相談窓口を利用することも選択肢として考えられます。また、信頼できる相手に相談することも重要です。
Q.バイトでパワハラを受けたことに対して、どの程度の被害なら損害賠償を請求できますか?
例えば、暴力や傷害によって負傷した、精神的な問題により出勤できなくなった、過度な要求やノルマによって健康を害した、このような場合は損害賠償を請求することができる可能性があります。
ハラスメントを受けた事実を証明するためには、医師の診断書や暴言の録音などの証拠を残すことが重要です。加害者だけでなく、使用者責任で企業や店舗のオーナーに対しても損害賠償を請求することができます。
5.監修者からのアドバイス
ハラスメントを受けたときは、相談時にその事実を説明するためにも、ハラスメントの発生日時、内容、目撃者などを記録に残し、可能であれば暴言などを録音しておくと有効です。
話し合いによって解決できる場合もありますが、難しければ信頼できる上司や家族、相談窓口に相談することをおすすめします。パワハラ防止法(労働施策総合推進法)の施行により、相談しやすい環境が整備されているため、悩んで一人で抱え込むことなく、気軽に相談してください。
6.まとめ
アルバイトの職場で働いていると、誰しもハラスメントに遭う可能性があります。心身共に健康で楽しく働き続けるためにも、どんなことがハラスメントに当たるのかという概要や、ハラスメントを受けてしまったときの対処法についても事前に学び、もしものときに備えておくことが大切です。
監修者

有限会社キャリアドメイン
代表取締役 キャリア・デベロップメント・アドバイザー(CDA)
谷所 健一郎(やどころ けんいちろう)氏
東京大学教育学部付属高校在学中にニューヨーク州立高校へ留学、武蔵大学経済学部卒業。大学卒業後株式会社ヤナセに入社し、大型雪上車の営業職として日本全国のスキー場を飛び回る。30歳で株式会社ソシエワールドへ転職し、その後一貫して人事に携わり、株式会社綱八人事部長を経て2005年に独立。1万人以上の面接経験から、就職・転職・人事・婚活に関する書籍を多く執筆し、セミナー・講演・求職者支援の他、企業向け人事コンサルティングを行う。