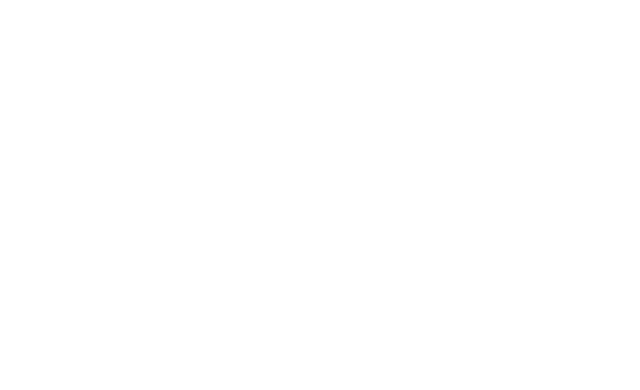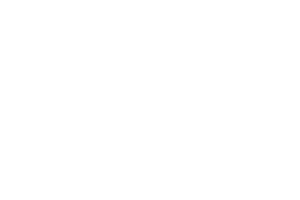「パートでも育休を取れるのかな…」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。本記事では、パートの育休取得条件やもらえる給付金、具体的な申請手続きの流れについて分かりやすく解説します。復職までの手順についても紹介するので、育児と仕事を両立させたい方はぜひ参考にしてください。
1.パートでも育休は可能
パート勤務の方でも一定の条件を満たせば、安心して育児休業を取得できます。
育児休業とは、子どもが1歳になるまでの間、仕事を休んで育児に専念できる制度です。育児休業制度は、育児・介護休業法で保障されており、正社員だけでなくパートの方も法律の対象となります。
また、保育園に入れないなど特別な事情がある場合、最長で子どもが2歳になるまでの休業期間延長も認められています。
2.パートが育休取得に必要な条件5つ
パート勤務の方が育児休業を取得するには、以下の5つの条件を満たす必要があります。
(1)雇用保険に加入している
育児休業を取得するためには雇用保険に加入している必要があります。パートの方が雇用保険に入るための条件は以下のとおりです。
- 週に20時間以上働いている
- 31日以上の雇用期間が見込まれている
週20時間未満の勤務の場合、雇用保険には加入できません。ただし、短時間勤務であっても、一定以上の勤務時間と雇用期間の見込みがあれば育児休業の取得は可能になります。
(2)勤務期間
パート勤務の方が育児休業を取得するためには、勤務期間に関する一定の条件があります。
- 申請時点で同じ職場に1年以上継続して勤務している
- 子どもが1歳6カ月になるまで契約が続く見込みである※有期契約の場合
いずれかを満たさない場合、育休を申請できないケースが多いでしょう。一般的に勤務期間が長いほど、パートでも育休を取りやすくなります。
(3)勤務実績
パート勤務の方が育児休業を取得するためには、勤務実績も重要です。具体的には、育休を開始する直前の2年間において「月11日以上勤務した月が合計12カ月以上あること」が条件になります。
上記の勤務実績がない場合は育休の取得対象外となるため、自分が条件を満たしているかどうか、事前に勤務記録をしっかりと確認しましょう。
(4)休業中の賃金
育休中は原則として会社から給与が支払われない、あるいは一部しか支払われない場合が多いです。
そこで、育休期間中の収入減少を補う「育児休業給付金」という制度があります。支給額は休業前の給与の67%(育休開始から6カか月間)または50%(6カか月以降)と定められていますが、育休期間中に通常賃金の8割以上が支払われていると、育児休業給付金の対象外になってしまいます。
育児休業給付金を受給するための条件を考え、育休中の収入や家計状況を把握しておきましょう。
(5)週の所定労働日数
パート勤務の場合、週に働く日数が少なすぎると育児休業の取得が難しくなります。具体的には、「週2日勤務以下」の方は育休の対象外になる可能性があるでしょう。
育児休業の取得条件は「一定の日数を継続して働くこと」を前提としているため、週1回や2回しか働いていない場合は、雇用保険にも加入できず、育休の資格を満たさないケースが多いです。
育休を取得するには、最低でも「週3日勤務以上」が必要だと理解しておきましょう。
3.パートが育休を取るメリット

ここからは、パート勤務の方が育休を取得するメリットを紹介します。
子育てと仕事を両立できる
子育てに専念している期間に退職すると、再就職先を探すのが難しくなり、ブランクによる不安や収入面での心配も出てくるかもしれません。ただし、育休を取得すれば、仕事を辞めずに一定期間育児に専念できます。仕事やキャリアも大事にしたい場合は育休取得が望ましいでしょう。
育休後に職場復帰できる安心感がある
育休の取得は職場復帰が前提のため、新たな就職先を探す必要がありません。会社によっては、育休取得後の従業員がスムーズに職場に復帰できるよう、柔軟な働き方の提案や職場環境の整備を行っているケースもあります。戻る場所があるという安心感は大きなメリットと言えるでしょう。
社会保険料免除や育児休業給付金などの経済的支援が受けられる
育休期間中は健康保険料や厚生年金の保険料が免除され、経済的な負担が減ります。また、育児休業給付金として最初の半年間は休業前の賃金の67%、その後は50%の給付を受けることが可能です。
社会保険料免除や育児休業給付金などの支援は国が保障しているもので、経済面が心配な方でも安心して育児に専念できるような制度が整っています。
参考:パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます|政府広報オンライン
参考:育児時短就業給付の内容と支給申請手続|厚生労働省
4.パートが育休を取るデメリット
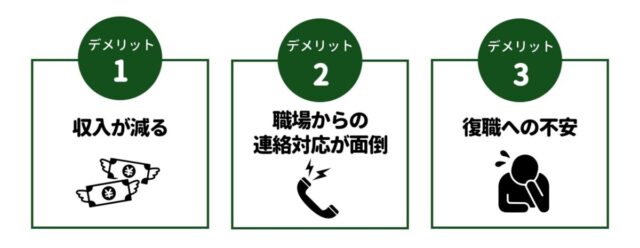
反対に、パート勤務の方が育休を取得するデメリットも見ていきましょう。
収入が減る
育児休業中は給付金が出ますが、普段の給料よりも金額が少なくなるため、生活費のやりくりに困る可能性が高いでしょう。
給付金の金額は育休前の給料の67%または50%なので、育休に入る前の収入と比べると大幅に減少します。家計の負担が大きい場合は、貯金を切り崩したり、パートナーの収入に頼ったりする必要が出てくるかもしれません。
あらかじめ生活費の見直しをしたり、節約の計画を立てたりするなど、収入が減った場合の備えをしておきましょう。
職場からの連絡対応が面倒
育休中でも、職場から業務に関する連絡や相談が来ることもあるかもしれません。育児に専念したい時期に仕事のことを気にするのは、心理的な負担になります。
会社と連絡頻度や連絡方法について事前に相談し、自分が負担に感じない範囲で対応できるように調整しておくと安心です。
復職への不安
自分が休んでいる間に職場環境や人間関係が変化していたり、元の業務に戻れるか心配になったりするかもしれません。また、育休中に新しいスキルや業務が増えている場合、自分がついていけるのかと不安を感じるケースもあります。
可能な範囲で会社と定期的なコミュニケーションを取ったり、復帰前に職場の状況を確認させてもらったりと、自分に合った対策を職場と検討してみても良いかもしれません。
5.パートの育休取得から復職までの具体的な手順6つ
育休を取得してからスムーズに職場復帰するまでは、主に6つの手続きが必要です。詳しい流れを見ていきましょう。
(1)育児休業取得の要件確認
会社側は、パート勤務の方が育児休業を取得できるかどうかの条件を確認します。具体的には雇用保険の加入状況や労働契約期間、勤務実績などです。
また、会社の就業規則に基づき、育休を取る際に必要な書類や手続きの確認も行われます。条件を満たしていなかったり、書類が不足していたりすると育児休業を取得できない場合もあるため、早めに会社側と連携して確認することが大切です。
(2)会社の就業規則確認
パート勤務の方自身も、育児休業を取得する資格があるかどうか、会社の就業規則でしっかり確認しましょう。会社の就業規則には、取得の条件や休業中の扱い、手続き方法が詳しく書かれています。
また、会社と労働組合などで交わされている労使協定がある場合には、労使協定の規則内容の確認も必要です。労使協定は、育児休業の取得条件や期間、対象となる労働者の範囲など、就業規則を補足する内容が記されています。
就業規則とあわせて労使協定も確認し、自分の取得条件や手続き方法を明確に理解しておきましょう。
(3)育児休業の申し出
育児休業を希望するパート勤務の方は、会社に対して育児休業を取得したい旨を申し出る必要があります。育休を始めたい日付の1カ月前までに「育児休業申出書」を会社に提出してください。
育児休業を予定通り取得するためにも、必ず期限を守って早めに提出することが重要です。
(4)育児休業給付金申請と社会保険料免除
育児休業中の経済的負担を軽くするため、会社側が「育児休業給付金」の申請手続きや社会保険料の免除手続きを行います。必要書類などがあれば速やかに会社に提出し、手続きを進めましょう。
(5)復職準備
育休期間が終わりに近づいたら、会社に復職したいことを伝えましょう。その際、会社と面談を行い、復職後の働き方や勤務時間について以下を具体的に話し合います。
- 復職後の具体的な働き方
- 勤務時間や時短勤務希望の有無
- 実際に働き始める日程
- その他の勤務条件
しっかり話し合うことで、復職後の不安や負担を減らせるでしょう。
(6)復職手続き
育休から復職する際には、以下の再手続きが必要です。会社が手続きを行うため、担当者に提出が必要な書類を確認しておきましょう。
- 健康保険・厚生年金保険の資格取得手続き
- 雇用保険の資格取得手続き
原則として育児休業前と同じ仕事に戻りますが、時短勤務など希望する勤務条件によっては、職務や部署が変わる可能性もあります。また、育休中に業務内容や職場のルールが変わっている場合もあるため、復職時に職場の状況を再確認しましょう。
6.パートの育休は条件と手続きを理解して取得しよう
今回は、パート勤務でも条件を満たせば育児休業が取得できることをお伝えしました。育休を取得できるか心配な方も、勤務期間や勤務実績・雇用保険への加入状況など、自分が条件を満たしているかを確認すれば、制度を安心して利用できます。
また、育休中の給付金や社会保険料の免除などのメリット、収入が減るといったデメリットを事前に把握しておくのも重要です。自分の勤務状況をしっかりと確認し、早めに会社や上司へ相談して、スムーズに職場復帰できる準備を整えましょう。