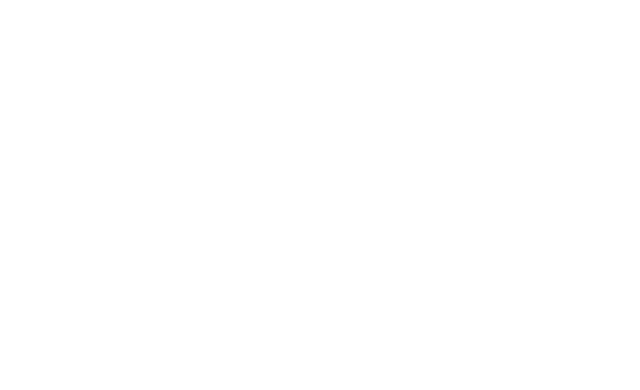「バイトでも有休は取れる?」「お客さまにうっかりおつりを多く支払ってしまったけど、これって私が自腹を切らないといけないの?」などアルバイトで抱きがちな悩みや疑問は、法律の知識を必要とするケースが少なくありません。
アルバイトをするうえで知っておきたい法律知識を、労働問題に詳しい弁護士・金東煥(きむ・どんはん)さんに教えてもらいました。
【金 東煥(きむ・どんはん)弁護士のプロフィール】

労働問題の解決を専門とする「旬報法律事務所」に所属。「外国人の労働問題」に興味を持ったところから弁護士を志し、中央大学法学部法律学科卒業後、神戸大学法科大学院修了。労働事件のほか、 インターネット上のトラブルや刑事事件も取り扱う。
【相談1】アルバイトでも有給休暇は取れるの?
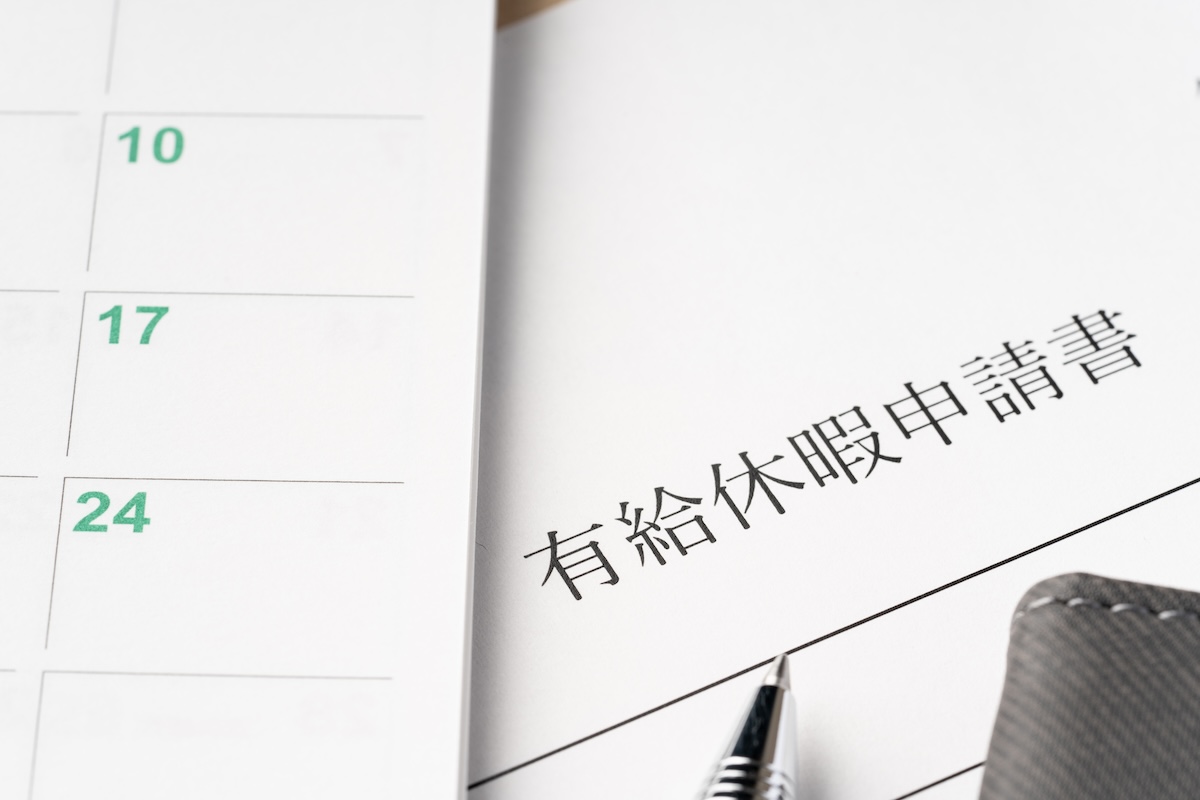
Q.「アルバイトでも社員のように有休が取れる」と先輩から教えてもらいました。これって本当ですか?
A.アルバイトでも、一定の条件を満たせば有給休暇が取れます
【金弁護士のアドバイス】
採用されてから6カ月間継続して働き、契約で定められた労働日数の8割以上出勤していれば、アルバイトでも有給休暇を取得できます。有休が実際に何日取れるかは、働いた年数や労働時間によって異なります。
有休についてきちんと案内してくれないケースもあるかもしれませんが、要件を満たしていれば法律上はOKなので、自信を持って「有休を取りたいです」と担当者に伝えてみてください。
もし拒否された場合は、最寄りの労働局や労働基準監督署に無料の「総合労働相談コーナー」があるはずなので、「要件を満たしているのに、バイト先が有休を取得させてくれない」と相談してみましょう。
【相談2】求人情報と実際の仕事の内容が違う

Q.店頭の求人情報を見てアルバイトに応募したのに、いざ働いてみると時給や仕事の内容が違っていました。店長に言っても「あれはあくまで一例だから」と取り合ってくれません。
A.労働条件に反する内容の業務をさせられている場合は、即座に「やめます」と伝えてOK
【金弁護士のアドバイス】
雇用主には労働時間や賃金を定めた「労働条件」を書面にし、働く人に対してきちんと示す義務があります。
もし「雇用契約書」が手元にない場合は、バイト先に確認してみてください。そのうえで、労働条件と異なる仕事をさせられている場合は、即座に「やめます」と伝えてもOKです。
「すこし慣れてきたと思ったら接客をワンオペで任されるようになってしまった」など、書面上の労働条件には反しないものの、働くうえで大きな負荷がかかっている場合も、「ワンオペでは難しいです」と上司や担当者に伝えてみてください。
雇用主には職場環境に配慮する義務がありますし、チェーン店や大きな会社の場合は社内に「労働組合」と呼ばれる団体が労働条件改善のために活動している場合もあります。
もし上司が相談に対応してくれないときは、そういった組合を頼ってみるのも手です。
【相談3】アルバイトも“残業”したら、給料が増えるの?

Q.普段は学校終わりに短時間だけアルバイトをしていますが、夏休みはバイト先が繁忙期で朝から夜までガッツリと働きました。これって残業代はもらえるんでしょうか?
A.勤務時間が1日8時間、週40時間を超えたらアルバイトでも残業手当がもらえます
【金弁護士のアドバイス】
アルバイトやパート、社員などの雇用形態に関わらず、「所定の労働時間」を超えて働いた場合は、残業代を支払う義務が雇用主にはあります。もし残業手当がもらえていなければ、まずは担当者に相談してみてください。
ちなみに、アルバイトのために制服や作業着を着用する必要がある場合や、休憩時間中に電話対応などの「業務」が発生した場合、その時間も労働時間に含まれます。
数時間単位ではないものの、勤務時間がわずかに長くなっているのに、それが給与に反映されていないケースもあるかもしれません。その場合は「〇月◯日の休憩時間に電話対応をした」など、簡単でも構わないのでなるべく記録を残しておくといいですよ。
【相談4】自分のミスでおつりをうっかり多く渡してしまったら……?

Q.バイト先で、お釣りをうっかり多くお客さまに渡してしまったところ、店長から「君のミスだから、その分は自腹で」と言われました。これって払うべき?
A.バイトのミスによる損失は会社が負担するもの。払う必要はありません
【金弁護士のアドバイス】
意図しないミスで損失を出してしまっても、アルバイトがその分のお金を払う必要はありません。職場では誰でもミスを犯す可能性があることはあらかじめ想定されているので、その分の損失は会社が負担することになっています。
「ミスした分の金額は給料から差し引きます」というケースも、労働基準法に違反しています。たとえミスが複数回起きてしまった場合も、バイト先には給与を全額支払う義務があります。
ただ、わざと会社に不利益を与えようとした場合は、損害賠償などを求められるケースもあります。
【相談5】やむをえず欠勤するときはピンチヒッターを探すべき?

Q.急な体調不良で「休みたい」と店長に連絡したら、「代わりに働ける人を探してほしい」と頼まれました。これって私がやらなきゃいけないことなんですか?
A.法律上は、休む人が“代わり”を見つける必要はありません
【金弁護士のアドバイス】
働く人の急なお休みに対して「代わりに働ける人」を探すのは、会社側やお店側の義務なので、法律上は自分で代わりの人を見つける必要はありません。
とはいえ、職場は働く人同士の協力で成り立っているもの。自分が入るはずだったシフトに穴を空けることを「申し訳ない」と感じ、自ら進んで代役を見つけることもあるでしょうから、そこはケースバイケースで対応しましょう。
急な体調不良など余裕がない場合は、心配せずにしっかり休んでくださいね。
ちなみに「辞めたいといったら『代わりの人を連れてきて』と言われた」場合も同様で、働く人の退職に合わせて新しい人を雇うのも、会社やお店側の義務です。
【相談6】バイト先に向かう途中でけがをしてしまった

Q.バイト先に向かう途中、自転車で転んでけがをしてしまいました。しばらくバイトするのは難しそうだし、治療代もかかりそう……。
A.通勤中のけがは「労災保険」が適用される可能性も
【金弁護士のアドバイス】
バイト先へ向かう途中やバイト帰りの道でけがをした場合、「労災保険」が支払われることがあります。
バイト先の上司や担当者に「けがをしたので労災を申請したいです」と伝えれば、状況を調査した上で労災の申請手続きをしてくれるはずです。ただし、途中で寄り道をするなど、業務に関係のない場所でけがをした場合は、労災認定は難しいので気を付けて。
もしもバイト先の上司や担当者が労災について詳しくない場合は、最寄りの労働基準監督署や弁護士に相談するなど、ぜひ専門家を頼ってみてください。
【相談7】店長から「もう来なくていい」と言われた。これってクビ?

Q.寝坊してバイトに1時間遅刻しちゃったら、バイト先の店長から「もう明日から来なくていいよ」と言われてしまいました。本当にやめなくちゃいけないんでしょうか?
A.まずは店長の言葉が「解雇」を意味しているかどうか、きちんと確認を
【金弁護士のアドバイス】
法律上、雇用主が働く人を「クビ」にするハードルはとても高く、基本的には一度の寝坊やミスなどで簡単に解雇はできません。
まずは「もう来なくていい、は解雇を意味していますか?」とバイト先の店長にあらためて確認して、それでも「解雇です」と言われた場合は、解雇理由を説明した文書を発行してもらいましょう。
理由に納得できない場合は、書類を持って最寄りの労働局や労働基準監督署にある「総合労働相談コーナー」に相談してみてくださいね。
気を付けてほしいのは、本当に解雇の意思があるかどうかを確認せず、自分から「わかりました、退職します」と言ってしまうケース。退職勧奨(退職するように雇用主が勧めること)に応じたとみなされてしまい、本来であればもらえたはずの賃金や保険などが受け取れなくなることがあります。
本当にアルバイトをやめたいとき以外は、「やめます」と安易に言わないようにしましょう。
【相談8】バイト先の先輩からしつこく誘われて困っている……

Q.バイト先に、やたらプライベートの遊びや飲み会に誘ってくる先輩がいます。すべて断るのも気まずいのでたまに応じたら、そのたびに「付き合っている人はいるの?」などとしつこく絡まれて困っています。
A.まずは職場で相談。でも相談しづらい場合は、専門機関を頼ってもOK
【金弁護士のアドバイス】
バイト先で「セクハラ」や「パワハラ」と感じる行為があったら、まずはバイト先の責任者に相談してみてください。雇用主には、働く人の環境に配慮する義務があります。
ただこういったトラブルは、人間関係が気になって直訴できない場合もあるはず。その際は、労働局に相談してみてください。
もしも適切な相談窓口がわからない場合は、Webから無料で利用できる「法テラス」から弁護士を案内してもらっても良いでしょう。心細かったら自分ひとりではなく、家族や友人と一緒に訪問しても大丈夫です。
相手から言われたことやされたことをメモしておいたり、可能であればLINEの記録などを残しておけると、職場に相談する場合も、専門機関に相談する場合もスムーズに進むと思います。
【相談9】バイト先の制服をSNSにアップするのはNG?

Q.バイト先の制服がかわいいので、店内のトイレで自撮りをして写真をSNSに投稿したら、お客さまからクレームが入ったと店長に注意されました。ただ自撮りをしただけなのに、納得できません。
A.どうしてもSNSに上げたいなら、許可を取った方がベター
【金弁護士のアドバイス】
SNSへの投稿は、時に大きなトラブルに発展することがあります。本人は「自身の制服姿を撮影するだけだから」と軽い気持ちで行ったとしても、店内やバックヤードで撮影した場合は、お客さまの顔やバイト先の機密情報が映り込んでしまう可能性も考えられます。
トラブルを防ぐためにも、写真を撮ったり、SNSに投稿したい場合は、責任者にきちんと許可をもらってからのほうが良いでしょう。
困りごとが解決しないときは、専門機関へ
トラブルから自分の身を守るため、新しくバイトを始める場合はできるだけ雇用契約書を発行してもらうか、自分の労働条件をきちんと確認しておきましょう。
また、専門機関に相談する場合は「証拠」や「記録」が大切になってきます。バイト先で受けた被害や気になったことをメモしておいたり、録画・録音などに残しておいたりすると、話がスムーズに進むでしょう。
【記事に登場した専門機関や団体の解説】
・労働局:労働者の権利を守ったり、労働条件の改善や労働災害の防止などを目的に、各都道府県に設置。労働者からの相談の受付を行っており、雇い主との間にトラブルが発生した場合は、アドバイスや話し合いの仲介をしてくれることも
・労働基準監督署:全国にあり、法律に基づき管轄地域の会社を調査・指導などするところ。労働基準法に違反しているトラブルで悩んでいる場合は、労働基準監督署へ相談するとベター
・総合労働相談コーナー:全国の労働局や労働基準監督署内に設置されている、無料の相談窓口。セクハラ・パワハラから解雇まで、働くうえで遭遇するさまざまなトラブルや悩みに、面談か電話で相談にのってもらえる。女性相談員の有無も事前にネットで確認可能
・労働組合:働く人が主体となり、賃金や労働時間などの労働条件の維持・改善のために活動している団体。「ある職場」と「ない職場」がある
・法テラス:国が設立した、法的トラブル解決のための総合案内所。労働問題に限らず、ありとあらゆるトラブルに悩んでいる方に、適切な相談窓口を紹介したり、無料で法律情報を提供したりしている。お金に困っている場合は、弁護士に無料で法律相談に乗ってもらえることも。問い合わせ方法は電話、メール、チャットなどさまざま
取材・文/生湯葉シホ
編集:はてな編集部