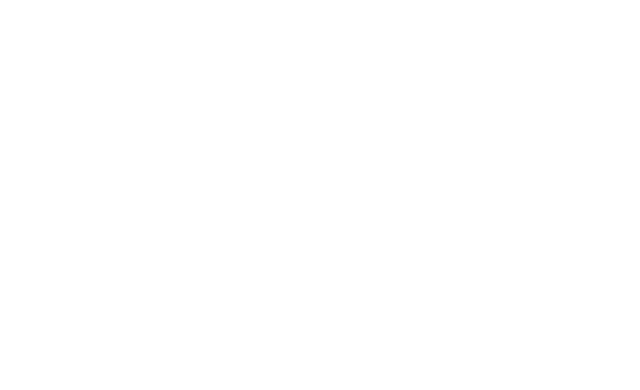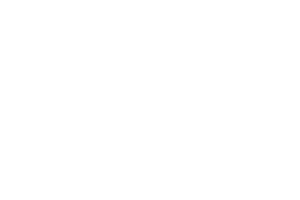正社員だけでなく、アルバイト・パートでも一定の条件を満たせば有給を取得可能です。本記事では、アルバイト・パートで有給が付与される条件や取得できる有給日数を紹介します。また、「アルバイトは有給がない」と言われた場合の対処法についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
アルバイト先で有給がないと言われたら?
有給とは「年次有給休暇」の略称で、労働者のリフレッシュを目的に労働基準法によって定められた休暇です。労働者は雇用形態に関わらず一定条件を満たせば有給を取得でき、会社側は申請を拒否できません。
しかし、繁忙期などで人手が足りない場合、会社側が有給希望日の変更を求めることは可能です。条件を満たしているのに「有給は使えない」と直属の上司に言われたら、バイト先やパート先の更に上の立場の人や人事担当者に相談してみましょう。
それでも拒否されてしまった場合は、管轄の労働基準監督署など公的な窓口へ相談するという方法もあります。
アルバイト・パートの有給取得条件
アルバイト・パートで有給を取得するためには、2つの要件を満たす必要があります。有給取得の要件については、労働基準法第39条によって規定が定められています。
(1)半年以上継続して働いている
アルバイト・パートのシフトが週1日だとしても、雇用日から半年以上続ければ要件を満たすことになります。
(2)所定労働日の8割以上出勤している
ここで言う所定労働日とは、契約によって決められている労働日数のことを指します。
例えば、「週4日」のシフトで「月17日」出勤している場合、半年間(6カ月)の所定労働日は17日×6カ月=102日となり、約82日出勤すれば8割以上の出勤率となります。
上記の例では、体調不良などでアルバイトを休んだとしても、82日以上出勤していれば、有給取得のための2つ目の要件を満たしていると判断できます。
参考:労働基準法第39条
アルバイト・パートが取得できる有給日数
アルバイト・パートで有給が何日もらえるかは、所定労働日数や勤続年数によって変わってきます。一般的には、勤続年数が長く、シフトが多く入っているほうが付与される有給が多い傾向があります。
週5日勤務の場合
1週間の労働時間が30時間以上で週5日勤務の場合、付与される有給の目安は以下のとおりです。
- 継続期間が半年:10日
- 継続期間が1年半:11日
- 継続期間が2年半:12日
- 継続期間が3年半:14日
- 継続期間が4年半:16日
- 継続期間が5年半:18日
- 継続期間が6年半以上:20日
週5日のフルタイムで勤務している場合は、半年以上経過した段階で有給が発生し、勤続年数に応じて最大で20日分有給が付与されます。
週1〜4日勤務の場合
1週間の労働時間が30時間未満で週1~4日勤務の場合、付与される有給の目安は以下のとおりです。
アルバイト・パートなどで週4日以内の勤務の場合、労働日数と継続期間に応じて付与される有給の日数が異なります。
| シフト | 週1 | 週2 | 週3 | 週4 |
| 半年 | 1日 | 3日 | 5日 | 7日 |
| 1年半 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 |
| 2年半 | 2日 | 4日 | 6日 | 9日 |
| 3年半 | 2日 | 5日 | 8日 | 10日 |
| 4年半 | 3日 | 6日 | 9日 | 12日 |
| 5年半 | 3日 | 6日 | 10日 | 13日 |
| 6年半以上 | 3日 | 7日 | 11日 | 15日 |
参考:年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか|厚生労働省
アルバイト・パートが有給でもらえる賃金の計算方法
有給を取得する場合、有給手当がいくらもらえるのかはバイト先やパート先の規則によって異なります。有給でもらえる賃金は、以下の3つの中のどれかで計算されるケースが多いでしょう。
(1)通常賃金から計算するケース
1つ目は、通常賃金で計算するパターンです。アルバイトやパートの場合は、時給×所定労働時間で計算されます。
出勤する曜日によって所定労働時間が異なる場合は、労働時間が多い曜日で有給を申請するほうが、その分もらえる賃金も多くなります。
計算例(時給1,000円で6時間勤務の場合)
1,000円×6時間=6,000円
(2)平均賃金から計算するケース
2つ目は、平均賃金から計算するパターンです。仮に、直近3カ月で計算する場合は、3カ月分の賃金の総額から勤務日数を割って計算します。
計算例(3カ月の給料の総額が20万円、合計勤務日数が40日の場合)
20万円÷40日=5,000円
(3)標準報酬日額から計算するケース
3つ目は、標準報酬日額から計算するパターンです。標準報酬日額とは、社会保険料を計算するために設定されている金額のことで、この計算方法を採用するケースは少ないかもしれません。
標準報酬日額から計算するのは、バイト先やパート先で健康保険に加入している場合のみで、あらかじめ労使協定(労働者と会社との間での協定)を結ぶ必要があります。
アルバイト・パートの有給に関するよくある質問
アルバイト・パートの有給に関するよくある質問について回答します。
Q.有給取得理由を聞かれたらどう答えればいい?
有給を使うことは労働者の権利であり、有給取得の理由を具体的に述べる義務はありません。一般的には「私用のため」「家庭の都合」などで問題ないでしょう。
Q.有給は何日前に申請すれば良い?
有給を使うときは日程が決まった時点でなるべく早めにバイト先に申請するほうがいいでしょう。シフトの調整も早ければ早いほどしやすく、同僚への負担も軽減できる可能性があります。
また、「有給の申請は〇日前までに」などバイト先によっては規定があるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
Q.有給を取らないほうがいい時期は?
有給は基本的にいつでも使えますが、繁忙期などに有給を使うのはなるべく避けたほうが良いでしょう。職場に迷惑がかからないように配慮し、時期を見ながら計画的に有給を使うのがおすすめです。
Q.アルバイトで有給消化はできる?
アルバイトを退職する際、残りの有給を消化することは可能です。ただし、有給を取得するタイミングによっては日程変更の相談をされるケースもあるため、事前に会社と相談しておくと安心です。
有給は計画的に使おう
有給は、労働基準法によって定められた労働者の権利です。アルバイトやパートでも要件を満たせば有給を取得することができます。ただし、有給を取得する際はシフトが決まる前など、早めに職場に申請することが大切です。
有給が付与されてから2年で有給の権利は消失してしまうので、計画的に有給を使っていきましょう。