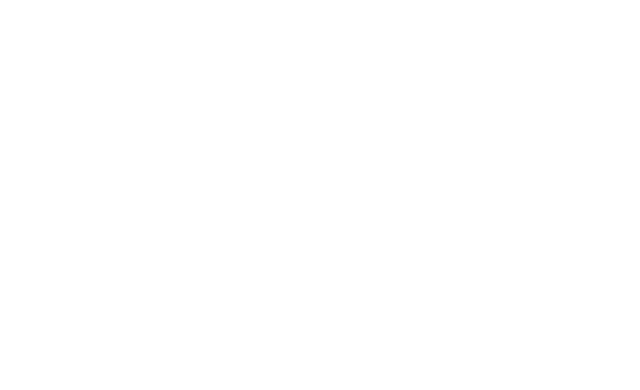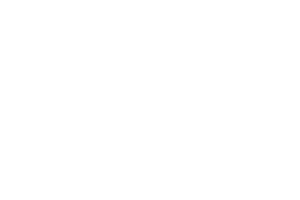この記事の要約
- 以下2つの条件を満たせばパートでも雇用保険に加入できる
- 雇用保険に加入するメリットは保険給付が受けられること
- 条件を満たしていながら雇用保険に加入しないのは違法
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上
(2)31日以上働く見込みがある
雇用保険に加入すると、失業時に各種給付が受けられたり、職業訓練が受けられたりといったメリットがあります。
本記事では、「パートでも雇用保険に加入できるの?」「加入できない人ってどんな人?」といった疑問を抱いている方に向け、パートで雇用保険に加入する際の条件と、加入した場合のメリット・デメリットについて分かりやすく解説します。パートで働く人はぜひ参考にしてみてください。
1.パートでも加入条件を満たせば雇用保険に加入できる

雇用保険は雇用形態に関わらず条件を満たせば誰でも加入する保険なため、パートという名称で雇用されても条件を満たしていれば加入できます。加入対象者がいる企業は、決められた期間内に手続きを行う決まりになっています。
そもそも雇用保険とは?
雇用保険とは、企業で働く労働者の雇用維持と生活の安定を目的とした保険制度です。正社員・アルバイト・パートにかかわらず、要件を満たす労働者はすべて被保険者となります。
雇用保険の加入条件は2つ
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上
所定労働時間とは、雇用契約によって定められた一定期間内の労働時間のこと。
例えば、残業などによって実際の労働時間が1週間で20時間以上になったとしても、もともとの労働条件が15時間など、20時間未満が通常の週所定労働時間なら、雇用保険の加入条件を満たすことにはなりません。
(2)31日以上働く見込みがある
雇用期間の定めがなく雇用される場合や、2カ月更新などで契約上の雇用期間が31日以上になる場合などが該当します。
また、仮に31日未満の雇用契約であっても、雇用契約によって「自動更新」など契約更新が明示されている場合や、更新規定がなくても過去に31日以上雇用されている実績がある場合も、「31日以上の雇用見込みがある者」として扱われます。
2.雇用保険と社会保険は何が違う?
【社会保険を構成する保険】
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 労働者災害補償保険
- 雇用保険
社会保険は社会保障制度の一つで、5つの保険の総称として使用される言葉です。「雇用保険」はこの社会保険に含まれていますが、社会保険のなかから「労働者災害補償保険」と「雇用保険」を取り出して「労働保険」として扱う場合もあります。
その場合の社会保険とは、「健康保険」「介護保険」「厚生年金」のことを指し、「狭義の社会保険」と呼ばれます。
【社会保険の目的】
社会保険は、国民が病気やケガ、出産、死亡、老齢、障害、失業などになった場合に一定の給付を行い、国民の生活が安定するように支援する公的保険制度。狭義の社会保険の加入対象は、従業員数が101人以上(※2024年10月からは51人以上の企業に対象が拡大)の企業で働く人で、以下の条件を満たす人です。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 1カ月の賃金が8.8万円以上(通勤手当などの手当や残業代は含まない。)
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生でないこと
一方、雇用保険はその業種や事業規模にかかわらず、労働者を1人でも雇用する場合はすべて適用事業所になります。農林水産業など一部適用が任意とされている業種もありますが、労働保険の適用は「労働者1人でも雇い入れていれば適用事業所」となるため、狭義の社会保険よりも適用範囲は広いと言えるでしょう。
3.パートで雇用保険に加入するメリット・デメリット

次に、パートが雇用保険に加入するメリットとデメリットについて紹介します。
【メリット】各種給付が受けられる
パートが雇用保険に加入する一番のメリットは、各種保険給付が受けられることです。保険給付のなかで最も知られているのが「基本手当」ですが、これは「失業手当」と呼ばれることがあります。(※以降、雇用保険は「失業手当」と説明しています)
失業時に一定の要件を満たすことで手当が支給されます。基本手当の受給要件は、以下のとおりです。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
(中略)
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12カ月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上ある場合でも可。※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1カ月と計算します。
引用:厚生労働省 ハローワークインターネットサービス 基本手当について
失業保険以外にも、育児休暇を取った際に受給できる「育児休業給付」や、仕事のスキルアップや資格取得のための講座費の一部が給付される「教育訓練給付」などもあります。また、失業保険を受けていた人が再就職した際には、要件を満たすことで「就職促進給付」も受給できます。
それぞれの保険給付を受けるためにはそれぞれの受給要件があるため、雇用保険に加入しただけでは受けられません。保険給付を受け取るためには、しっかりと受給要件を確認しておきましょう。 各種保険給付以外にも、就職が困難な人には無料で職業訓練を受けられるなど、雇用保険に加入することで労働者にうれしいサービスが受けられます。
【デメリット】手取りが少なくなる
雇用保険は加入することで不利益になることはありませんが、雇用保険料を毎月支払うことになるため、デメリットと感じる人もいるかもしれません。
ただし、 雇用保険料は全額自己負担ではなく、事業主と労働者がそれぞれ負担する形になっています。仮に控除前の給料が10万円とすると、月々の給料から控除される雇用保険料は「10万円×6÷1000(一般事業の雇用保険料率)=600円」となります。手取りが少なくなるとはいえ、天引きされる金額自体は少額なため、メリットの方が大きいといえるでしょう。
4.パートの雇用保険料の計算式
パートの雇用保険料の計算式は以下のとおりです。
-
雇用保険料=支給総額(雇用保険対象賃金)×雇用保険料率
参考:雇用保険料率について
参考:雇用保険料の計算式
5.パートで雇用保険に加入できないケース

ここでは、パートで雇用保険に加入できないケースについて紹介します。
(1)加入条件を満たしていない場合
1週間の所定労働時間が20時間未満の人や、31日以上雇用されることが見込まれない人は、雇用保険に加入する必要はありません。
例えば、働く前から契約期間が25日と決まっていて、更新しないことが明示されている場合は、「31日以上の雇用見込みはない」と判断できるため、雇用保険に加入できません。
(2)昼間の学生の場合
高等学校・大学・専修学校に通っている昼間学生は、雇用保険の適用除外となります。ただし、昼間学生であっても、卒業前に内定先で働くことが決まっていて、卒業後に引き続き勤務することが決まっている場合や、休学中の場合などは、条件を満たせば雇用保険に加入できます。
また、通信教育・夜間・定時制の学生は、昼間の学生ではないため、こちらも条件を満たせば雇用保険に加入できます。
(3)季節的に一定期間雇用される場合
季節的に一定期間雇用される労働者で、4カ月以内に期間を定めて雇用される場合や、1週間の所定労働時間が30時間未満の場合は、雇用保険の適用除外となります。季節的な雇用とは、例えば「冬季限定」「夏季限定」など、自然現象の影響を受ける一定期間の仕事に雇用される人のことを指します。
6.雇用保険加入から失業保険を受けとるまでの流れ
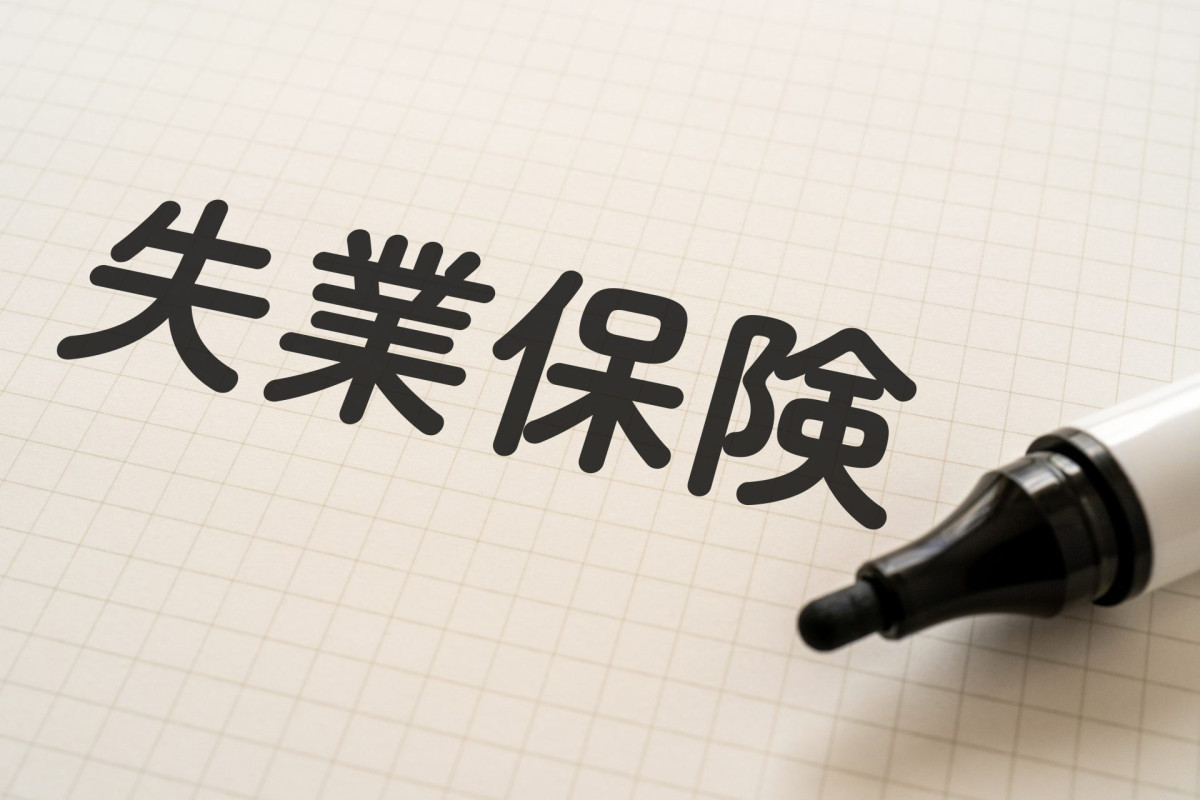
パートでも雇用保険に加入していた人が失業した場合は、条件を満たせば失業手当(基本手当)を受給できます。失業手当は、失業中でも生活の安定を図りつつ、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない間に支給される保険給付です。
加入期間が条件を満たせば失業手当の対象に
失業手当を受給するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- (1)失業の状態であること
- (2)離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上ある
「失業の状態」とは、就職したいという意思がありながら、職に就くことができない状態のことを指します。病気・ケガ・妊娠・出産・育児などですぐに就職ができない状態や、本人の意思によって就職を希望しない場合は該当しません。 保険給付は、被保険者期間が離職日以前の2年間で12カ月以上ある人が対象です。
ただし、会社の都合によって解雇・退職した場合や、自己の都合によりやむを得ない事情によって離職し、「特定受給資格者」もしくは「特定理由資格者」に該当するとハローワークが判断した場合には、被保険者期間が6カ月以上あれば受給できるケースもあります。
失業手当を受けとるまでの流れ
失業手当を受けとるためには、自分で手続きを行う必要があります。失業手当を受けとるまでの主な流れは、以下のとおりです。
- ①離職前に離職証明書の準備を会社に依頼する 「雇用保険被保険者証」の有無を確認し、企業がハローワークに提出する「離職証明書」の離職理由の内容を確認する)
- ②離職後、「雇用保険被保険者離職票」を企業から受けとる
- ③住所地管轄のハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みを行う
- ④受給資格が決定。受給説明会を受ける
- ⑤待期期間と給付制限経過後、4週間に一度ハローワークへ行き、失業状態の確認を行う。失業とは原則として認定対象期間中、原則として2回以上求職活動を行う
- ⑥失業認定後、失業手当を受給
失業保険は、手続きをすればすぐに受け取れるわけではありません。ハローワークが行う職業相談・職業紹介・各種セミナーに参加、資格試験の受験や求人への応募などをして、求職活動の実績から「求職の意思および能力がある」と判断された場合に受給可能となります。
7.条件を満たしていても入れない場合は?

雇用保険の加入条件を満たしていても加入していない場合は、勤務先の担当者に相談しましょう。
パート先の人事担当者に確認する
雇用保険は、加入条件を満たしていれば会社や労働者の意思に関係なく加入しなければならない強制保険です。そのため、加入条件を満たしているのに雇用保険に加入しないのは違法になります。もし加入できるはずの雇用保険に加入していない場合は、パート先の上司や責任者に相談しましょう。
相談するときは勤怠の記録や給料明細など、加入条件を満たしていることが分かるものがあるとスムーズです。担当者が雇用保険の加入条件をよく知らなかったことが理由で加入できていなかったのであれば、相談することで問題解消につながります。
ハローワークへ相談する
勤務先の担当者に相談しても解決しなかった場合は、最寄りのハローワークに相談しましょう。ハローワークでは適正に企業が雇用保険の手続きを行っているか、照会できる仕組みが設けられています。
また、電子申請も可能 です。失業手当を受給するためには、雇用保険の被保険者期間の要件が給付の条件となります。雇用保険の適用対象であると証明できれば、一定期間遡って雇用保険に加入できるケースもありますので、不安な人は早めにハローワークに相談しましょう。
8.パートの雇用保険から外れることはある?
パートで雇用保険に入っている場合、条件によって雇用保険から外れることがあります。具体的な条件や流れは以下のとおりです。
所定労働時間が短くなった場合に雇用保険から外れる
所定労働時間が一定の基準を下回ると、雇用保険から外れることがあります。雇用保険の加入条件は、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」が基本です。つまり、何らかの理由でシフトを減らして週20時間未満の勤務になった場合、雇用保険の被保険者ではなくなります。
例えば、これまで週25時間で働いていた方が、家庭の事情で週16時間の勤務に変更した場合、雇用保険の加入条件を満たさなくなるため、雇用保険から外れることになります。
ただし、労働時間の減少が一時的で、週20時間以上に戻る見込みがある場合は外れません。
離職票が発行される
雇用保険から外れる際には、離職票が発行されます。離職票は通常、勤務先の会社から管轄のハローワークに届け出が行われた後、会社を通じてあなたに渡されます。離職票の発行には手続きの時間がかかるため、すぐに手元に届くわけではありません。一般的には、雇用保険から外れてから約10日〜2週間程度で受け取れるでしょう。
離職票は、後に失業給付を受ける際に必要となるため大切に保管してください。万が一紛失してしまった場合、ハローワークでの再発行が可能です。
失業給付を受給できるようになる
雇用保険から外れた場合、条件を満たしていれば失業給付を受給できます。失業給付を受けるためには、主に以下の条件を満たす必要があります
- 離職前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること
- 積極的に求職活動を行っていること
- 疾病や負傷のために働くことができない状態でないこと
パートタイマーが勤務時間の短縮によって雇用保険から外れた場合でも、上記の条件を満たせば失業給付を受けられます。ただし、自己都合による離職の場合は、給付開始まで3カ月の待機期間が設けられるため、注意が必要です。
9.パートの雇用保険に関するよくある疑問
最後に、パートの雇用保険に関するよくある疑問について回答します。
Q.雇用保険の手続きは誰が行う?
雇用保険の加入手続きを行うのは、労働者本人ではなく勤め先の会社です。雇用した従業員の加入手続きを怠った場合は、罰則になる場合もあります。労働条件が変わって新たに雇用保険に加入する場合、逆に雇用保険の対象外となる場合には、その都度会社側が手続きを行う必要があります。
Q.1週間の労働時間が、20時間以上と20時間以内でバラつきがある場合は?
雇用保険に加入するためには、「1週間の所定労働時間が20時間以上」となっています。所定労働時間とは、就業規則や雇用契約で定められている労働時間ですので、たまたま20時間未満になる週があったとしても、すぐに加入資格が失われるわけではありません。
1週間の所定労働時間が月によって変動する場合は、所定労働時間の平均を1週間の所定労働時間として判断します。仮に、1週間の所定労働時間が20時間未満でも、20時間以上の勤務が2カ月間続き、今後もその状態が続く見込みがあれば、3カ月目から加入対象となる場合もあります。
Q.あえて加入しないのは違法?
雇用保険は加入条件を満たせば本人の意思に関係なく加入する強制保険のため、加入条件を満たしていながら加入しないのは違法です。どうしても雇用保険には加入したくない場合は、雇用保険の加入条件を満たさない労働条件で働く必要があるでしょう。
パートの場合は、「1週間の所定労働時間」を、例えば「週3日・1日5時間=15時間」など、20時間未満の範囲で働くという方法があります。
10.雇用保険に加入できるか確認しよう
雇用保険は、さまざまな理由で離職・失業した人の生活と雇用の安定をサポートするための保険制度です。パートでも加入条件を満たせば雇用保険に加入でき、失業時には一定条件を満たせば各種給付の対象となります。雇用保険に加入できるかどうかについては、企業のパートの雇用方針にもよりますので、パート先の担当者に確認しておくと安心です。
監修者
社会保険労務士 行政書士 CFP(R)
昭和女子大非常勤講師 當舎 緑(とうしゃ みどり)氏
https://tosha.grupo.jp/