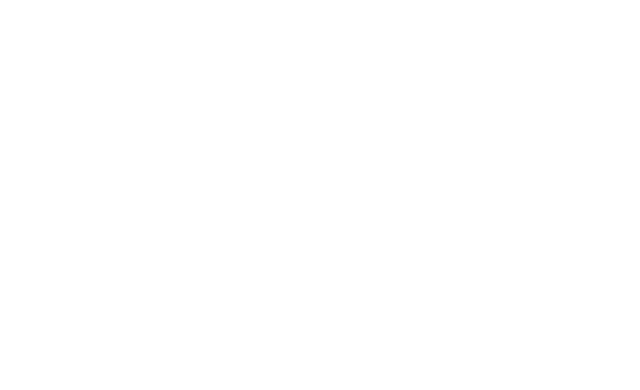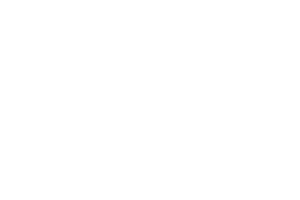この記事の要約
- 社会保険は一定の要件を満たすと加入義務が発生する
- 社会保険に加入するメリットは「もらえる年金額が増える」「保険料が安くなる場合がある」
- 社会保険に加入するデメリットは「扶養に入っている場合は手取りが減る」
- 「パートの社会保険加入条件が68,000円になる」という話は公式発表されていない(2024年5月時点)
パートとして働く際、社会保険に加入するべきかどうか悩む人も多いのではないでしょうか。本記事では、社会保険の内容と加入条件、加入したほうが良い&加入しないほうが良いケースについて紹介します。シニア世代が注意しておくべき制度もあわせて解説するので、チェックしてみてください。
1. 65歳以上のパートが社会保険に加入する際の条件とは?

社会保険とは、国民の失病や死亡、老齢、介護、労働災害、失業などに対して保障を行う公的な保険制度のこと。これには、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類が存在します。そのうち、狭い意味として一般的に「社会保険」と呼ばれることが多いのは医療保険と年金保険です。
この「狭義の社会保険」は、個人の意思で加入を判断する民間の生命保険などとは異なり、次のいずれかの要件を満たすと加入義務が発生します。
(1)1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の人
所定労働時間とは、就業規則などによって定められた始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間を差し引いた労働時間のこと。所定労働日数についても同様に正社員が基準となり、これらが正社員と比べて4分の3以上ある場合は、パートやアルバイトでも狭義の社会保険に加入しなければなりません。
(2)(1)には該当しない人で、次の5つの要件をすべて満たす人
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
- 1カ月あたりの所定内賃金が8万8000円以上であること
- 雇用期間の見込みが1年以上であること
- 学生ではないこと
- 従業員数が501名以上の会社で働いている、または従業員数が500人以下の会社で働いており、社会保険への加入が労使で合意されていること
所定内賃金とは、賞与や残業代などの変動的な賃金は含まず、あらかじめ決まっている基本的な賃金です。契約書などで分からない場合は、「時給×1週の所定労働時間×52週÷12カ月」で計算できます。 また、ここでの労使の合意とは、短時間労働者が社会保険に加入することについて、労働者の2分の1以上の同意を得た上で、事業主が年金事務所に申し出ていることをいいます。
(2)の条件を満たしていれば、パートやアルバイトをしていて(1)に当てはまらない方でも社会保険に加入できます。また、これらの条件に基づく社会保険の適用範囲は今後も段階的に拡大される予定です。
2. 2022年に社会保険の適用範囲が拡大!何が変わった?

2022年には、社会保険制度にいくつかの変更が導入され、社会保険の適用範囲が拡大しました。これにより、より多くの人々が社会保険の恩恵を受けられるようになりました。
「雇用保険」の加入条件
前年度の所得が100万円以上の個人事業主も雇用保険への加入が義務付けられました。これにより、個人事業主も雇用保険の失業手当や雇用安定給付金などの給付を受けられます。
「健康保険」の加入条件
一定条件を満たす学生や専業主婦・主夫も、配偶者や世帯主の健康保険に加入できるようになりました。これにより、これまで保険に加入できなかった人々も医療費の一部を補償してもらえるようになりました。
「厚生年金保険」の加入条件
前年度の所得が100万円以上の個人事業主も厚生年金保険への加入が義務付けられました。これにより、個人事業主も将来の年金を受け取る資格を得ることができます。
従業員数100人超の企業の社会保険の加入条件
これまでの制度では、従業員数500人超の企業が社会保険の加入対象でした。しかし、2022年以降は従業員数100人超の企業も加入対象となりました。
従業員数100人超の企業は、社会保険の各種保険料を支払う義務が生じます。更に、2024年には50人超の企業も加入対象になる予定です。
3. 65歳以上のパートが社会保険に加入するメリット

もらえる年金額が増える
社会保険に加入せず、配偶者や子どもの扶養に入っていたり、自営業などで国民年金のみの加入であったりする場合、将来的には国民年金しか受け取れません。しかし、社会保険の厚生年金保険に加入していれば、その分上乗せされた年金を受給することができるでしょう。
ただし、厚生年金保険の被保険者資格には「70歳まで」という年齢制限があります。シニア世代で将来的な年金の受給額アップを目指す人は、なるべく早く社会保険(厚生年金保険)に加入するのがおすすめです。
配偶者が社会保険に加入していない場合、保険料が安くなる
配偶者が自営業や個人事業主、または定年などによって会社を退職している場合、配偶者の扶養に入ることはできません。いずれも国民健康保険と国民年金の対象になるため、保険料の支払いは全額自己負担することになります。自身が社会保険に加入すれば、その保険料の支払いが企業と折半になるため、負担が軽くなる可能性が高いでしょう。
医療保険(健康保険)が充実する
国民健康保険から健康保険(社会保険)に切り替えることで、医療費の自己負担が軽減されるケースもあります
一般的に、国民健康保険は世帯単位で保険料が計算されるため、収入が多い家族がいると保険料が高くなりがちです。一方、健康保険は個人の収入に応じた保険料となるため、パートとして働く高齢者にとっては負担が軽くなることが多いでしょう。
保険料の半分は事業者負担が負担してくれる
国民健康保険では保険料の全額を被保険者自身が支払わなければなりませんが、健康保険では保険料の半分を会社が負担します。
例えば、月額の保険料が20,000円の場合、自己負担額は10,000円となり、残りの10,000円は会社が支払います。事業主負担があることで、実質的な手取り収入が増える効果があります。
4.65歳以上のパートが社会保険に加入するデメリット
扶養に入っている場合は手取りが減る
配偶者や子どもが社会保険に加入している人は、その扶養に入れば給料が一定の金額を下回る場合、社会保険料を支払う必要がありません。扶養に入っている人が自分で社会保険に加入すると、保険料の支払いが発生して給料の手取り額が減るため、逆に損をしてしまう可能性も考えられます。
具体的には、年収が106万円(条件次第では130万)を超えると社会保険料の負担が発生してしまうので、扶養内で働きたい人はこの額を超えないように注意してください。
介護保険の保険料が上がる
65歳以上のパートが社会保険に加入すると、介護保険料の負担が増加する場合があります。介護保険料は、40歳以上65歳未満の方は医療保険(健康保険や国民健康保険)と一体で徴収されますが、65歳以上になると原則として年金から天引きされます。しかし、社会保険に加入すると、給与からも介護保険料が徴収されることになります。介護保険料の算定方法が変わることで、収入に応じた負担となり、パート収入が一定以上ある場合には保険料が上昇することがあります。
特に、年金収入だけの時と比べて総収入が増えることで、より高い所得段階に区分され、結果的に介護保険料の負担が大きくなるケースが少なくありません。このため、社会保険加入によって手取り収入が思ったほど増えない場合もあります。
国民年金の任意加入ができなくなる
65歳以上のパートが社会保険に加入すると、国民年金の任意加入ができなくなるというデメリットもあります。通常、65歳以上70歳未満の方は、年金受給権の有無や加入期間にかかわらず、国民年金に任意加入できます。これにより、満額の老齢基礎年金を受けるための加入期間(40年)に足りない分を追加で納付できるようになるのです。
しかし、社会保険(厚生年金保険)に加入すると、この国民年金の任意加入ができなくなります。厚生年金保険の加入者は、同時に国民年金の第2号被保険者となるため、任意加入の対象から外れることを覚えておきましょう。
5. シニア世代が知っておくべき制度

シニア世代が社会保険に加入する場合、収入額によっては年金の受給額が減って損をしてしまう可能性があります。また、年齢制限によって一般的な保険制度の対象から外れる可能性もあるので、該当する制度はしっかりチェックしておきましょう。
在職老齢年金
在職老齢年金は、60歳以上の人が厚生年金保険に加入しながらもらえる年金のこと。働きながら年金ももらえると聞くとうれしい制度のように思えますが、実はこの年金は本人の年齢や収入額によって減額、または全額給付停止される可能性があります。収入額によって減額率は異なりますが、以下に該当する人は対象となるので注意しましょう。
「60歳~65歳未満」の場合
年金の基本月額(加給年金を除いた年金年額÷12)と総報酬月額相当額(賃金月額+年間賞与÷12)の合計が28万円以上になると減額対象になります。
「65歳以上」の場合
年金と総報酬月額相当額が47万円を超えたら減額対象になります。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、75歳以上(※)の人すべてが対象となる医療制度です。74歳までは、健康保険に加入していた人も、国民健康保険に加入していた人も、75歳になるとすべて後期高齢者医療制度の対象となります。
この制度は、都道府県ごとに医療水準に応じた費用を負担するため、格差が少なく公平であるというメリットがあります。一方、後期高齢者医療制度に加入する人が被保険者あるいは被扶養者であった場合、この制度に加入するとこれらの資格を失うことになります。条件に当てはまる方は勤務先の健康保険担当者や加入中の健康保険組合などで資格喪失の手続きが必要になるため注意しましょう。
※一定の障がいがある人は65歳から
6. パートの社会保険に関するよくある質問
Q.パートの社会保険加入条件が68,000円になるのはいつ?
パートの社会保険加入条件が68,000円になるという話は公式発表されていません。 2021年以降に、加入条件が引き下げられるという噂がありましたが、2024年5月時点では月収88,000円以上、年収106万円以上が社会保険の加入条件となっています。
Q.パートで社会保険に加入したくない場合の対策は?
社会保険は条件を満たさなければ加入義務はありません。「夫の扶養から外れたくない」などの理由で社会保険に加入したくない場合は、「月収約88,000円未満」「年収106万円未満」、週の労働時間を「20時間未満」に収めましょう。
7. まとめ
シニア世代が社会保険に加入するかどうかを決める大きなポイントは、扶養に入ることができるかどうかと、年金の受給額でしょう。配偶者や子どもの扶養に入っているうちは、その方が得なケースも多いかもしれません。
しかし、扶養に入っていない人や、将来的な年金の受給額を少しでも増やしたい人は、早めに社会保険への加入を検討するのも一つの手です。その際、もらえるはずだった年金をもらえなくなってしまわないように、在職老齢年金の減額などには注意してください。
関連情報として、高年齢求職者給付金についての情報もチェックしておきましょう!
取材協力・監修
あすか社会保険労務士法人
特定社会保険労務士 大東 恵子(おおひがしけいこ)氏
https://www.all-smiles.jp/