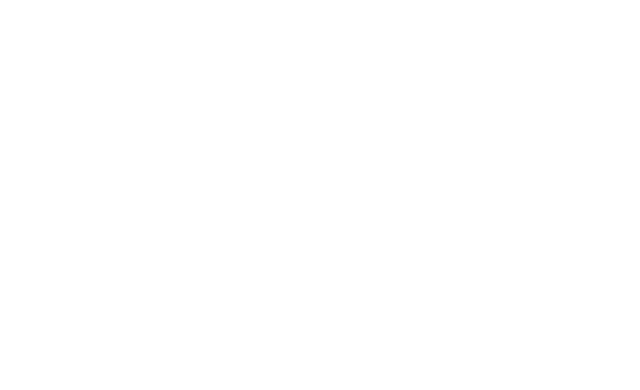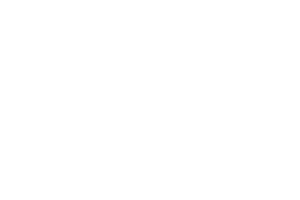アルバイトをしていると誰でも1度はミスをしてしまいますが、強く咎められ、罰金や減給、天引きといったペナルティを課されたことはないでしょうか。ミスをしてしまったという罪悪感がある手前、ついついペナルティに応じてしまいがちですが、法律は雇用者に対し、そのような強制力を認めてはいません。本記事では、ミスを犯してペナルティを課された場合の違法性について専門家が解説します。
1.【実例4選】バイト先でのペナルティの違法性
今回は本当にあったペナルティの実例から、その違法性の有無について「ブラックバイト対策弁護団」の一員である中川匡亮弁護士に検証していただきました。
【実例1】売上金の誤差を自腹で補填

■コンビニ店員Aさんの場合
「アルバイト先のコンビニで、レジのお金に1000円以上の誤差があると、アルバイトたちのポケットマネーで補填させられます。先日は1万円を超える誤差が発覚し、その日のバイト代がパーになってしまいました……」
■中川弁護士の見解
勝手に罰金などを天引きすることを禁じる「賃金全額払いの原則」に違反!これは法的観点で「会社は労働者のミスに対して損害賠償請求をできるのか」という問題に位置付けられます。会社は、労働者が働くことで利益を出しており、言い換えれば、「本来、経営者が自分でやるべき作業を労働者に代わりにやってもらっている」ということになります。仮に経営者自身が業務にあたっていたとしてもミスは生じるでしょうから、労働者のミスで損害が出た場合に、その補填を労働者に強いるのは不公平です。レジの計算ミスは普通に仕事をしていれば当然、生じうるミスですから、その損害をアルバイトに負担させることは許されません。たしかに1万円以上の誤差はなかなか起こりえないミスかもしれませんし、場合によってはアルバイトに一部負担させることが適法となる可能性もありますが、それでも全額負担は認められないでしょう。ちなみに、損害額を給料から差し引くことは、勝手に罰金などを天引きすることを禁じる「賃金全額払いの原則」(労基法24条1項)に違反します。
【実例2】遅刻と病欠で3000円天引き

■スーパーマーケット店員Bさんの場合
「学校の補習が長引き、バイトの時間に30分遅れてしまいました。更に後日、風邪を引いて急遽アルバイトを休んだら、合わせてペナルティとして給料から3000円天引きすると言われました。これは仕方がないと受け入れるしかないのでしょうか?」
■中川弁護士の見解
「権利を濫用」にあたり懲戒処分が無効になる場合もペナルティとしての減給処分ですが、労働法的には「懲戒としての減給」に位置付けられます。これは懲戒処分の1種で、場合によっては有効ですが、客観的合理性を欠き、社会的相当性がない場合、懲戒処分は「権利を濫用」にあたり無効となります。これは労働契約法15条が定めるところです。今回のバイトの遅刻について、学校の補習が長引いて遅刻することがあることを事前に伝えてあり、当日も遅刻する旨を連絡していたのであれば、減給は行き過ぎた懲戒処分で無効だと思われます。風邪での欠勤についてもやむを得ないことですから、懲戒処分には相当しないと考えられます。
【実例3】お皿1枚につき300円の罰金

■飲食店員Cさんの場合
「私のバイト先の中華料理店は、お皿1枚の破損につき300円の罰金というルールが設けられています。忙しい時間帯はお客さまの食べ終わったお皿が大量に運ばれてきますし、過去には洗い場に積み上げたお皿が倒れて10枚以上も同時に割れてしまったことも。3000円以上も罰金を払うなんてツライです…」
■中川弁護士の見解
仕事上のミスについて弁償額を決めておくことは禁止されている労働基準法16条は仕事上のミスについてあらかじめ弁償額を決めておくことを禁止していますので、「お皿1枚の破損につき300円の罰金」というルールは無効となります。ちなみにこの条文は、見習い期間に退職した人に対して、それまでの研修料を支払わせることなどを防止する規定としても重要ですので、アルバイトを始める前に予備知識として覚えておいたほうが良いでしょう。
【実例4】遅刻・欠勤が続き減給
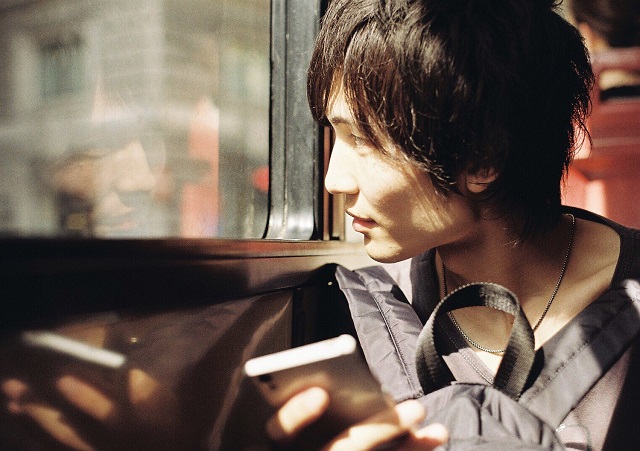
■ドラッグストア店員Dさんの場合
「大学のサークル活動が忙しく、アルバイトの遅刻や欠勤が続き、先日ついに減給を言い渡されてしまった……もっと時給の高いバイト先を探そうかな」
■中川弁護士の見解
遅刻や欠勤が続いていると減給処分となることもこちらもBさんと同様、客観的合理性を欠き、社会的相当性がない場合、減給処分は無効とされます。しかしDさんの場合は遅刻や欠勤が続いているため、減給が適法となる余地はありそうです。ちなみに、懲戒処分としての減給が認められる場合でも、一定の「制限」はあります。1回のミスにつき、平均的な1日分の賃金の半分以下、つまり平均して1日に1万円の給与をもらっている人は5000円以下の減給が限度と定められているのです。また、複数のミスがある場合でも、減給の総額は月給ごと(厳密には一賃金支払期ごと)の賃金の10分の1以下でなければならず、つまり給料の月平均が10万円であれば、減給は1万円以下の範囲内でなければなりません。これは労働基準法91条が定めているところです。
2.減給されても違法にならないケース4選
ここからは、バイトで減給されても違法にならないケースについて紹介します。
(1)懲戒処分による減給
懲戒処分による減給とは、従業員に対する制裁として本来支払われる賃金から一定額を差し引くことです。「無断欠勤を繰り返す」「セクハラをする」といった問題行動を起こした時に、懲戒による減給が行われることがあります。ただし、懲戒による減給処分は、就業規則に懲戒処分の種類や根拠を定めておく必要があります。また、減給される金額は「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」「総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定められています。(労働基準法91条)
(2)従業員との合意による減給
「業績が悪化した」などの理由から、会社側が一方的に従業員の給料を減額することは違法です。しかし、従業員が減給することやその金額に合意した場合は適法となります。
(3)管理職からの降格による減給
降格による減給には、「懲戒処分としての降格」「人事権行使としての降格」の2種類があります。「懲戒処分としての降格」は、問題行動を起こした際の制裁として行われる処分で、「証拠がなければ無効」「就業規則で降格理由を定めておく必要がある」などのルールがあります。一方、「人事権行使としての降格」は、役職に不適任な従業員を役職から外す処分であり、原則として会社の自由な判断で可能となっています。
(4)出勤停止処分による減給
問題行動による減給よりも重い処分として、出勤停止処分があります。例えば、問題行動による出勤停止10日という懲戒処分をした場合、その期間の給料は支払われません。また、出勤停止の懲戒処分の場合は、懲戒処分としての減給のように「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」というルールが存在しないため、勤務しなかった日数分の給料が支払われないということになります。
3.バイトのペナルティに関するまとめ
ペナルティにはさまざまな制限があり、雇用者側は自分の好き勝手なルールを労働者に押し付けることはできません。 そして、労働者側も勤務怠慢を続ければ懲戒処分とされる場合があることがお分かりいただけたと思います。お互いに良好な雇用関係を築くためにも、ぜひ参考にしてください。
取材協力

中川匡亮弁護士(ブラックバイト対策弁護団)
執筆・監修
猿川 佑氏
ジャーナリスト、雑誌編集者。
政治・社会問題からライフスタイルやファッションまで、扱う分野は多岐にわたる。