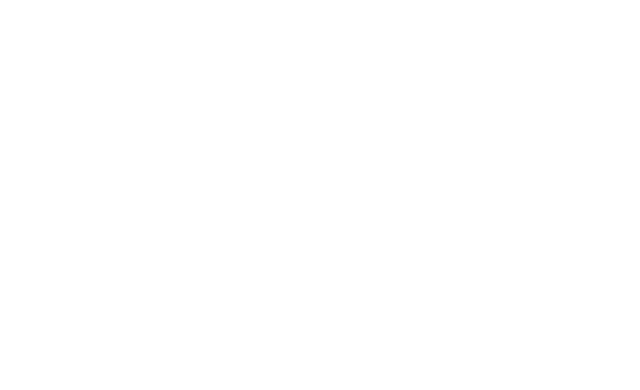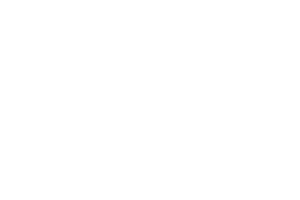目次
- 1. 123万の壁とは?わかりやすく解説
- 年収の壁とは?
- 103万円の壁とは?
- 123万の壁とは?
- 2. なぜ123万円?引き上げ決定の根拠
- 3. 123万の壁への引き上げはいつからいつまで?
- 4. 123万円の壁になると手取りや社会保険・住民税はどうなる?
- 【年収別】123万の壁へ引き上げた場合の減税額の試算
- 123万の壁による手取りへの影響
- 123万の壁による社会保険料への影響
- 123万の壁による住民税への影響
- 123万円の壁による大学生への影響
- 123万の壁によるパートで働く主婦(夫)への影響
- 5. 123万の壁に関するよくある質問
- Q.123万の壁は月いくらが目安?
- Q.103万の壁はいつから廃止される?
- Q.106万の壁とは?
- Q.130万の壁はいつから廃止される?
- Q.150万の壁とは?
- Q.160万の壁とは?
- 6. 年収の壁の引き上げを意識して働こう
2025年2月4日に、年収103万円の壁を123万円へ引き上げることが閣議決定され、そこから与党による政府案の修正を経て、最終的には2025年に160万円への引き上げが決定されました。
本記事では当初の案であった「123万の壁」について、いつから適用されるのか、引き上げられた場合はどのような影響があるのかなどについて解説します。年収の壁によって労働時間を調整している主婦(夫)や学生の方は、ぜひ参考にしてください。
1. 123万の壁とは?わかりやすく解説
123万円は当初の政府案であり、議論されていた所得税の非課税限度額は与党による政府案の修正を経て「160万円」へ引き上げられます。
ここでは、もとの案である123万円の壁について、以下の項目に沿ってわかりやすく解説します。
年収の壁とは?
年収の壁には、以下3種類の壁が存在します。
- 税金に関わる壁
- 社会保険に関わる壁
- 配偶者の被扶養者認定に関わる壁
税金や社会保険料の支払いによって手取り金額が減らないよう、収入を抑える目安の金額が「年収の壁」です。
例えば、会社員の配偶者などで、一定の収入がない被扶養者(第3号被保険者)は社会保険料を負担していません。これらの人のアルバイトやパートで得た収入が一定額を超えた場合、所得税の納税義務や、配偶者の被扶養者から外れて、社会保険料の支払い義務が発生します。
このボーダーラインが年収の壁であり「103万円の壁」や「130万円の壁」などと呼ばれています。
103万円の壁とは?
年収の壁のうち「税金に関わる壁」とは、所得に対して税金が課税される仕組みのことです。2025年1月現在では、年収103万円を超えると所得税が発生するようになっており、これを「103万円の壁」と言います。
具体的には、所得税を計算する際の基礎控除(48万円)と、給与所得控除の最低額(55万円)の合計金額の103万円です。所得税が発生すると、扶養している人も配偶者控除や扶養控除が受けられなくなるため、世帯全体の税負担が増えるリスクがあります。そのため、年収を103万円以内に抑えようと、労働時間を調整するパートの主婦(夫)やアルバイトの学生が多いのです。
なお、配偶者の年収が103万円を超えた場合は、配偶者控除に代わり配偶者特別控除が適用されます。配偶者の年収に応じて、配偶者控除に比べて控除できる額が少なくなっていくことも把握しておくと良いでしょう。
123万の壁とは?
| 103万円の壁 | 123万円の壁 | |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 48万円 | 58万円 |
| 給与控除 | 55万円 | 65万円 |
「123万円の壁」とは、103万円の壁と同様に所得税が発生する基準です。基礎控除も給与所得控除の最低額も10万円ずつ引き上げられ、控除額が合わせて20万円引き上げられる方針が決定しています。
2. なぜ123万円?引き上げ決定の根拠
日本社会の現状を踏まえて、年収の壁の議論が始まったのがきっかけで123万円の壁への引き上げが検討され始めました。
現在の日本では人材不足や子育てにかかる家計への金銭的な負担、物価の上昇といった問題が深刻化しています。年収103万円の壁は1995年から30年間変わっていませんでしたが、最低賃金は1995年と比較して611円(※1)から1,055円(※2)へと1.73倍になっています。
控除合計額も1.73倍に引き上げるべきと考えられたことを背景に「103万円×1.73=178万円」への引き上げが検討され始めました。
制度創設当初と比較して、生活必需品を多く含む基礎的支出項目の消費者物価指数が20パーセント程度上昇したことを踏まえ、引き上げ金額は123万円に着地しました。
※1 参考:厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」 ※2 参考:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
3. 123万の壁への引き上げはいつからいつまで?
123万円は当初の政府案であり、国会で修正されたため、所得税が課される基準は2025年分の所得から123万円→160万円に引き上げられることとなりました。
2025年分については、年末調整で対応される見込みです。
4. 123万円の壁になると手取りや社会保険・住民税はどうなる?
ここからは、もとの案である123万円の壁が及ぼすさまざまな影響についてについて解説します。
【年収別】123万の壁へ引き上げた場合の減税額の試算
103万円の壁から123万円の壁へ引き上げを行った場合の「減税額」を年収別で紹介します。
第一生命経済研究所の「『年収の壁 103万円→123万円』へのコメント~住民税の基礎控除分離は再考の余地~」によると、年収と減税額の関係は以下のとおりです。
| 年収 | 減税効果 |
|---|---|
| 400万円 | 5,000円 |
| 600万円 | 10,000円 |
| 800万円 | 20,000円 |
参考:第一生命経済研究所の「『年収の壁 103万円→123万円』へのコメント~住民税の基礎控除分離は再考の余地~」
例えば「会社員1名・配偶者の収入なし・子どもは中学生以下」のケースでは、年収400万円で年間約5,000円の減税が見込まれています。
123万の壁による手取りへの影響
減税額分だけ手取りが増えることになるため、先ほどのケースであれば年間5,000円ほど手取り金額が上がる想定になります。令和5年度の日本の平均年収が460万円※であることを考えると、手取りの増額効果は5,000円程度にとどまる世帯が多いと考えられるでしょう。
123万の壁による社会保険料への影響
年収の壁は、税金に関わる壁だけでなく「106万円の壁」と「130万円の壁」と呼ばれる社会保険に関わる壁も存在します。それぞれの壁に対する影響について確認しておきましょう。
123万の壁と106万円の壁
106万円の壁は、従業員数51人以上の企業における社会保険加入条件の一つです。 アルバイト先が「特定適用事業所」の場合、年収106万円を超えると、親や配偶者の社会保険上の扶養から外れて、社会保険料の負担が生じます。
123万の壁に引き上げられた場合、年収123万円まで所得税の支払いは避けられますが、勤め先によっては106万円を超えた段階で社会保険料を支払う義務が発生します。年間15万円程度の社会保険料がかかるため、世帯の手取りは減少するでしょう。
123万の壁と130万円の壁
130万円の壁は、「特定適用事業所」に限らず、親や配偶者の社会保険上の扶養から外れて、社会保険料の支払い義務が発生する基準です。
123万の壁への引き上げであれば影響しませんが、年収が130万円を超えると社会保険料(年間18万円程度)を支払う必要があるため、家計への負担が大きくなる点には注意しましょう
123万の壁による住民税への影響
住民税の支払い義務が発生する基準額は「100万円の壁」と呼ばれています。自治体によって基準が多少異なる場合がありますが、住民税を支払う義務が発生するのは、基本的には年収が100万円を超えた時点です。
今回の123万円引き上げの税制改正大綱では、所得税の給与所得控除が10万円上がるのと同時に、住民税の給与所得控除額も10万円引き上げられています。つまり、住民税の非課税の判定が上がった可能性があるでしょう。
123万円の壁による大学生への影響
123万円への引き上げが行われ、もし学生アルバイトの年収が123万円を超えてしまうと、扶養する親は扶養控除が受けられなくなります。そのため、2025年度から「特定親族特別控除(仮称)」が新設され、子どもの年収が一定額に達するまでは、引き続き扶養控除と同額の控除が受けられる予定です。
具体的には、16歳以上23歳未満の学生が150万円未満の年収があった場合でも、親の税負担が増えない措置となっています。もし150万円を超えた場合であっても、およそ187万円までは段階的に控除額が受けられ、188万円を超えると控除額がゼロになる仕組みが導入されます。
サービス業や飲食業で人手不足が深刻化しているため、学生の労働時間の縛りが緩和されることで、人手不足の緩和も期待できるでしょう。
以下の記事では、大学生におすすめのアルバイトを紹介していますので、ぜひご覧ください。
関連記事:大学生におすすめのバイト27選|平均時給ランキングや選び方のコツも解説
123万の壁によるパートで働く主婦(夫)への影響
扶養家族がいる場合、会社員は配偶者手当を支給されることがあります。手当支給の要件は会社によってさまざまですが、主婦(夫)や子どもなどの扶養家族の年収が103万円または130万円を超えると、支給の対象外となるケースが多いです。
厚生労働省が公表している「令和2年就労条件総合調査 」によると、扶養手当・家族手当・育児支援手当などの従業員1人あたりの平均支給額は月額1万7,600円です。年間21万1,200円の手当がなくなると、家計への負担になる可能性があります。
以下の記事では、主婦(夫)のアルバイトの探し方を解説していますので、ぜひご覧ください。
関連記事:【マイナビ直伝】主婦(夫)さんにおすすめのパートの探し方!子育てとの両立を実現
5. 123万の壁に関するよくある質問
最後に、123万の壁に関するよくある質問を2つ紹介します。
Q.123万の壁は月いくらが目安?
123万の壁とは、所得税に影響する年収の境界線です。この壁を超えると、収入に対して税負担が急増するポイントとなります。
月収の目安としては、約10万3000円がこの壁にあたります。具体的には、パート収入が月に約10万3000円を超えると、所得税の対象となり、税負担が増加します。
議論されていた所得税の非課税限度額は、与党による政府案の修正を経て、160万円と決定されました。当初の政府案が、この123万円となります。
Q.103万の壁はいつから廃止される?
103万の壁は2025年度分の収入から廃止され、160万の壁に引き上げられる予定です。2025年度分については160万円までの収入でも所得税がかからない見込みのため、年収と時給を換算し、労働時間を調整すると良いでしょう。
103万の壁の廃止については、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひチェックしてみてください。
関連記事:【簡単解説】103万の壁はいつ廃止?超えたらいくら払う?
Q.106万の壁とは?
106万の壁とは、従業員数51人以上の企業で、パート・アルバイトの年収が106万円を超えると社会保険の加入対象となることを指します。従業員数51人以上の企業で、以下の条件を満たす場合には、106万円の壁を超えることになり、社会保険の加入対象となります。
- 月額賃金88,000円以上
- 雇用見込み2ヵ月超
- 週所定労働時間20時間以上
- 学生ではない
一定規模以上の企業でパートやアルバイトして働く場合には、月額賃金88000円を目安にすると良いでしょう。
関連記事:「106万円の壁」とは?年収の壁をわかりやすく解説【バイト用語集】
Q.130万の壁はいつから廃止される?
社会保険の「106万の壁」について、撤廃する案を厚生労働省が審議会の部会に示し、2024年12月に了承されました。2026年10月をめどに、年収を問わず、週20時間以上働く労働者が社会保険の加入対象となる見込みです。このため、「130万の壁」についても同様の影響を受けることが考えられます。
Q.150万の壁とは?
150万の壁は、パートやアルバイトで働く配偶者の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除が完全になくなる境界線です。また、2025年度の税制改正により、特定扶養控除の年収上限額が150万円に引き上げられることから、こちらも150万の壁と呼ばれます。年収が150万円を超えると、配偶者のいる世帯主は税制上の優遇を一切受けられなくなるため、世帯全体の税負担が急増します。具体的には、世帯主の所得税と住民税が上がり、手取り収入が減少する可能性があります。
例えば、年収1,000万円の夫がいる場合、妻の収入が150万円を超えると、世帯全体で約10万円の税負担増になることもあります。
ただし、自身のキャリア形成や将来の年金受給額を考えると、この壁を意識しつつも、長期的な視点で収入を増やす選択をすることも大切です。パート勤務の際は、この壁を理解した上で、自分のライフプランに合った働き方を選びましょう。
関連記事:【社労士監修】年収150万円の壁とは?パートで働くときの年収のポイントについて解説
Q.160万の壁とは?
所得税が発生する境界である103万の壁が引き上げられたものです。当初の政府案は123万円でしたが、与党による修正を経て、160万円と決定されました。年収に応じて段階的に基礎控除が変更され、年収が200万円以下であれば、最大の95万円となります。この額と給与所得控除の65万円を合計した額が160万となることから160万の壁と呼ばれます。
160万の壁は、2025年度税制改正によって適用されるため、それ以降は月収約13万3千円を目安に収入調整すると良いでしょう。
関連記事:2025年から制度が変わる!アルバイトの住民税は年収いくらから発生する?支払い方や金額シミュレーションを解説
6. 年収の壁の引き上げを意識して働こう
所得税の課税基準は、当初の政府案である123万円から、与党による修正を経て「160万円」と決定されました。その分、パートやアルバイトで稼げる金額が増えるのはメリットでしょう。
しかし、106万円を超えた時点で、社会保険料の支払い義務が発生するといった別の年収の壁による影響も受けることとなります。手取り金額が減らない程度にシフトを調整し、パートやアルバイトを行えるようにしましょう。
年収の調整がしやすいアルバイトを探すなら、条件検索が可能なマイナビバイトがおすすめです。 案件豊富なマイナビバイトで、扶養内で働ける理想的な条件のアルバイトを探してみましょう。
取材協力・監修

涌井社会保険労務士事務所
社会保険労務士
涌井 好文(わくい よしふみ)
https://sr325012538.wordpress.com/