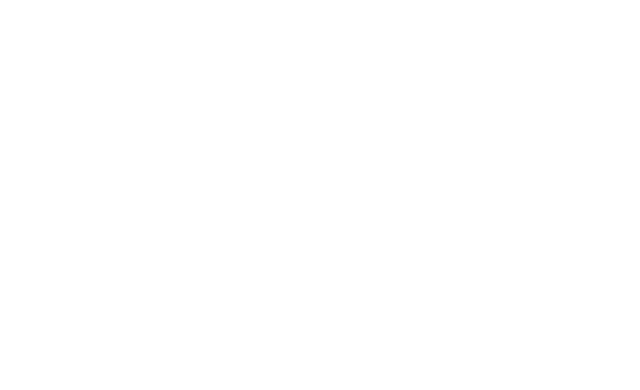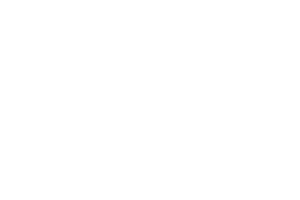パート収入や副業収入に対して、確定申告の必要があるかどうか分からないわからない人も多いでしょう。自分は確定申告の対象外だと思っていても、パートを辞めたタイミングや給与以外の所得額によっては、申告が必要な場合もあります。
この記事では、パートとして働いている人向けに「確定申告の対象となる条件は?」「確定申告をしないとどうなるの?」といった疑問について解説します。確定申告の手続きについても紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
1. パートで確定申告が必要となる6つの条件
まずは、パートで確定申告の必要となる6つの条件について解説します。
(1)年収が103万円を超えている
パートで働いた1年間の収入が103万円を超えると、確定申告が必要な場合があります。年収が103万円を超えると納税の義務が発生し、所得税を申告しなければなりません。これがいわゆる『103万円の壁』です。
『103万円の壁』については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
>>>【簡単解説】103万の壁はいつ廃止?超えたらいくら払う?
年収が103万円を超えていても、勤務先で年末調整をしていれば確定申告手続きは不要です。しかし、年末調整をしていない、またはパートを掛け持ちしている場合は確定申告手続きをする必要があるため注意しましょう。
(2)年末調整前にパートを辞めた
勤務先で年末調整をする前にパートを辞めた場合は、確定申告が必要となります。勤務先での年末調整対象となるのは、その年の12月31日時点で在籍している従業員です。そのため、12月31日以前にパートを辞めている場合は、自分で確定申告の手続きを行う必要があります。
パートの年末調整書類の書き方については以下で詳しく解説しています。
>>>パートの年末調整の書き方|パートナーの扶養内のケースや記入例を解説
パートを辞めるまでの年収が103万円以下の場合は確定申告不要となるので、自分の年収はしっかり把握しておきましょう。
(3)パート先で年末調整ができなかった
期日までに勤務先で年末調整ができなかった場合は、確定申告の対象となります。パートで稼いだ年収が103万円を超えている人は、勤務先で年末調整ができるよう期日までに書類を提出しましょう。年収103万円以下であれば、課税対象外のため確定申告は任意となりますが、源泉徴収されている場合は申告することで所得税の還付が受けられます。
(4)掛け持ちで働いている
掛け持ちして働いている人は、すべての収入を申告するために確定申告をしなければなりません。複数の勤務先に在籍している場合、年末調整をするのはそのうち1社のみです。そのため、年末調整をおこなった勤務先以外の収入については確定申告が必要となります。
なお、すべての勤務先の合計年収が103万円以下、または年末調整をしていない勤務先での年収が20万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。
(5)年間20万円以上の副業所得がある
ブログ運営・クラウドソーシング・フリマアプリなどで得た副業所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。パート先で年末調整をした人も、副業所得については自分で申告しなければなりません。
なお、パート収入が年間103万円以下の場合でも、副業所得が年間20万円を超えるのであれば確定申告の対象となります。日ごろから副業収入について記録しておき、漏れのないように申告しましょう。
(6)1年のあいだに医療費の支払いがあった
以下の条件にあてはまる人は、確定申告をすると医療費控除が適用されます。
- 1年間の医療費が10万円を超えている
- 年収200万円未満で、医療費が所得の5%を超えている
申告できる医療費には、診察代や入院費はもちろん通院に使った車のガソリン代なども含まれます。そのほか、健康診断や歯の治療、はり・きゅうやマッサージにかかった費用も控除対象です。
累進課税制度により、収入の高い人が控除を受けると多くの還付を受けられるため、節税効果を高めるなら生計同一者のなかでもっとも年収の高い人が申告すると良いよいでしょう。
2. 【パート向け】確定申告のやり方
確定申告の手続きをスムーズに進めるにあたって、必要書類や提出方法を事前にしっかり確認しておくことが大切です。ここからは、パートで働いている人向けに確定申告のやり方を解説します。
事前準備:確定申告に必要な書類
確定申告の手続きをする前に、まずは以下の書類を準備しましょう。
| 確定申告書 | 管轄の税務署および国税庁のHPから入手 |
| マイナンバーカード | 通知カードまたは住民票+運転免許証などの写しでも可 |
| 源泉徴収票 | パート勤務先で発行される |
| 控除証明書 | 契約している保険会社などから送付される |
| 銀行口座情報 | 税金の還付先とする口座情報 |
必要書類をすべて準備したら、確定申告書を記入して税務署へ提出します。確定申告には3パターンの提出方法があるので、自分に合った方法で期日までに提出しましょう。
提出方法①e-Taxによる電子申告
税務署へ行かなくても足を運ばなくても、e-Taxを利用すればスマホやパソコンから確定申告の手続きが可能です。
e-Taxとは、所得税などの国税に関する手続きがインターネット上で行える国税庁運営のサービスです。e-TaxソフトまたはWEB上で申告データを作成し、マイナンバーカードを用いて電子署名をしたデータを送信すれば確定申告が完了します。税務署窓口は確定申告の期間になると混み合いやすくなるため、e-Taxによる電子申告が便利です。
提出方法②税務署窓口へ持参
税務署窓口へ確定申告書を直接提出するのもひとつの方法です。税務署窓口に行けば、記入方法や不明点を担当者に確認しながら確定申告書の作成ができます。ただし、自分の納税地を管轄している税務署に行かなければ、確定申告手続きはできません。一般的に、納税地は住民票記載の住所と同一です。
どの税務署が自分の納税地を管轄しているのかは国税庁のホームページから確認できるので、事前に確認しておきましょう。また、期日が近づくと税務署窓口はかなり混雑するため、余裕をもって行動するのがおすすめです。
提出方法③税務署へ郵送
確定申告書は、管轄の税務署もしくは業務センター宛ての郵送でも提出できます。確定申告書は『信書』扱いとなるため、かならず『郵便物(第一種郵便物)』か『信書便物』として郵送しましょう。
なお、返信用封筒を同封のうえ確定申告書を郵送すると、申告書を収受した日付と税務署名が記載されたリーフレットが返送されます。このリーフレットは確定申告書を提出した証明となるので、紛失しないように保管しておきましょう。
3. パートが確定申告をする時の注意点
確定申告をする際に漏れや見逃しがあると、損をしてしまう可能性があります。ここからは、パートが確定申告をする際に注意すべきポイントを2つ紹介します。
すべての所得をもれなく申告する
確定申告をする際は、すべての所得を申告しましょう。パート収入のみ、または副業所得のみなど特定の所得だけを申告すると、申告漏れとみなされて無申告加算税が課される可能性があります。
また、申告内容の修正が発生した場合は別途延滞税が課されるため、確定申告書は間違いのないように作成しましょう。申告漏れがあると納める必要のなかった税金が課される可能性があるので、特にパートの掛け持ちや副業所得を得ている人は注意が必要です。
退職金は場合によって申告が必要となる
退職金は原則として確定申告不要ですが、場合によっては申告手続きが必要です。パート勤務でも、就業規則によっては正社員と同様に退職金が支給されることがあります。
退職金は退職所得に該当し、支払者に申告書を提出すれば源泉徴収で課税されるため、確定申告の手続きは不要です。ただし、年末調整をしていない場合や医療費控除などを受けるために確定申告をする際は、退職所得も一緒に申告しなければなりません。
4. 確定申告ってなに?
確定申告とは、1年間の収入に対して納めるべき所得税を正しく算出し、申告する手続きのことです。1月1日から12月31日までの給与収入が103万円を超える場合、納税の義務により確定申告が必要となります。パートであれば勤務先で行う年末調整で所得税を申告することがほとんどですが、本記事でも紹介しているとおり、場合によっては個人での確定申告が必要です。
確定申告書の提出期間は翌年の2月16日から3月15日ごろとなっているので、該当する場合は忘れずに申告しましょう。
5. 確定申告と年末調整の違いとは
| 確定申告 | 年末調整 |
| 自分で所得税の計算から申告手続きまでを行う | 勤務先が従業員の所得税を計算して手続きを行う |
確定申告と年末調整は、どちらも1年間の所得税を正しく清算するための手続きです。確定申告は個人の所得税を申告するものであり、所得税の計算から申告手続きまでを自分で行います。一方、年末調整は勤務先が従業員の所得税を計算して手続きを行うため、パートとして働いている場合は基本的に確定申告手続きは不要です。
勤務先で年末調整をしてもらうためには、自分で書類を記入する必要があります。書類の書き方が分からない人は、「パートの年末調整の書き方|パートナーの扶養内のケースや記入例を解説」をご覧ください。
6. 確定申告をしないとどうなるの?
もし確定申告をしなかった場合、罰則等はあるのでしょうか。ここからは、確定申告をしないとどうなるのかをパターン別に解説します。
確定申告が必要なのに申告しなかった場合
確定申告が必要にもかかわらず期日までに申告がなければ、税務署長により所得金額および税額が決定されることがあります。また、期日後の申告には加算税が課せられる場合があるほか、申告期限の翌日から申告日までの延滞税を納付しなければなりません。
意図的に確定申告の手続きをしなかった場合には、脱税とみなされて重加算税が課せられたり逮捕・起訴されたりする可能性もあります。重いペナルティを受けることのないよう、申告漏れに気づいた時点ですみやかに確定申告手続きをしましょう。
そもそも確定申告が不要の場合
- 医療費控除
- 住宅ローン控除
- 寄附金控除
パート先で年末調整をしているなど、確定申告が不要の人は申告手続きをしなくても基本的には問題ありません。ただし、確定申告をすることで以下の還付を受けられます。
また、パートを退職したことなどが原因で源泉徴収されすぎている場合も、確定申告をすると払いすぎた所得税が戻ってきます。確定申告の対象外でも、申告手続きをすることで還付金を受け取れる可能性があるので、自分が控除対象かどうかをしっかり把握しておきましょう。
7. パートでも確定申告が必要であればかならず期限内に申告しよう
パートとして働いている人も、年収が103万円を超える場合や掛け持ちなどの働き方によっては確定申告が必要です。
パート・アルバイトで確定申告が必要な人の条件については、以下で詳しく紹介しています。
>>>【税理士監修】アルバイトでも確定申告が必要な人ってどんな人?無申告時のペナルティも覚えておこう
確定申告の対象でありながら申告を漏らしてしまうと、本来納める必要のない税金を課される場合があるため、期日を守って申告手続きをおこないましょう。確定申告書の提出は、税務署に直接書類を持っていく以外にもe-Taxによる電子申告や郵送といった方法があります。「忙しくて税務署に行く時間がない……」という人でも簡単に申告手続きができるので、正しく所得税の還付を受けるためにも、しっかりと確定申告をおこないましょう。
確定申告不要の扶養内で働けるパートを探すなら、求人情報が豊富なマイナビバイトがおすすめです。