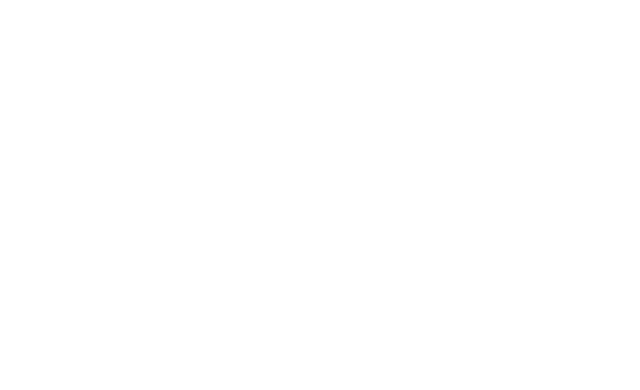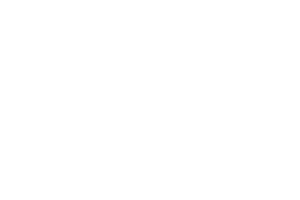多くの大学生が参加するインターンシップ。よく話題に上がるものの「インターンに参加する理由が分からない」「アルバイトとどう違うの?」と思う人も多いのではないでしょうか? この記事では、インターンシップとアルバイトの違いや、インターンシップに参加するメリット、職業例について詳しく紹介します。
1. インターンシップとは

インターンシップは、学生が企業などで就業体験をすることです。その目的は、自分にその仕事が向いているかどうかを見極めたり、社会人としてのマナーやスキルを習得したりすること。今後のキャリア形成に備えて、多くの学生がインターンシップに参加しています。
インターンシップは2種類
2023年からインターンシップの制度が新しくなり、2025年3月に卒業予定の学生から新制度が適応されます。これまで一括りに「インターンシップ」と呼ばれていたものが、新制度では「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」と「高度専門型インターンシップ」の2種類に分けられるようになります。
汎用的能力・専門活用型インターンシップ
汎用的能力・専門活用型インターンシップは、多くの学生が参加できるインターンシップで、主に企業で実務体験を行います。その内容によって更に細分化され、学生の適性や汎用的能力を重視する「汎用的能力活用型インターンシップ」と、より専門性を重視する「専門活用型インターンシップ」があります。
それぞれ実施期間が定められていて、汎用的能力活用型インターンシップは5日以上、専門活用型インターンシップは2週間以上です。学業との両立に配慮して、学部3・4年生および修士1・2年生の長期休暇期間に行われます。
高度専門型インターンシップ
高度専門型インターンシップは、修士・博士課程を対象にし、特に高度な専門性を求められる実務を職場で体験するインターンシップです。理系の博士課程を対象とした「ジョブ型研究インターンシップ」と、文系の修士課程学生を対象とした「高度な専門性を重視した修士課程学生向けインターンシップ」(仮称)に分けられます。
ジョブ型研究インターンシップの実施期間は2カ月以上の長期と定められています。一方、高度な専門性を重視した修士課程学生向けインターンシップの実施期間は現在検討中ですが、2週間以上の長期で行う方向で検討されています。
その他、「オープン・カンパニー」「キャリア教育」もある
インターンシップには該当しませんが、学生のキャリア形成支援として「オープン・カンパニー」「キャリア教育」という取り組みもあります。
- オープン・カンパニー:業界や企業理解を深めるための説明会やイベント
- キャリア教育:キャリア形成について考えるための教育を目的としたプログラム。大学の授業や産学協同プログラム、1〜3日間ほどの仕事体験などがある
これらは必ずしも就業体験が含まれるわけではなく、インターンシップよりも気軽に実際の仕事や企業の雰囲気を知ることができるものとなっています。学部・修士・博士課程の全期間で参加できますが、学部1・2年生などの早い段階から積極的に参加してみると良いでしょう。
学生のインターンシップ・仕事体験参加率は約85%!
2025年3月卒業予定の大学3年生、大学院1年生(2,633名)を対象に実施した「マイナビ 2025年卒大学生広報活動開始前調査」によると、学生がインターンシップ・仕事体験に応募した割合は91.0%、参加した割合は85.7%でした。特に参加した割合は2014年卒の学生を対象にした調査開始以来の最高値で、最近の学生にとってインターンシップ・仕事体験への参加が一般的なものになり、年々参加者が増えていることが分かります。
2. インターンシップとアルバイトの違い

インターンシップは学生が就業体験によって自分の適性や仕事内容を理解することが目的となるため、収入を得るために行うアルバイトとはそもそもの位置付けが異なります。インターンシップとアルバイトの違いを詳しく解説していきましょう。
給与の有無
アルバイトは給与が支給されますが、インターンシップは給与が支給されるものと支給されないものがあります。長期にわたるインターンシップであれば、実際に企業の一員のような形で仕事を任されるので、労働の対価として給与をもらえることが多いようです。
インターンの給与体系には、時給・日給・成功報酬系などがあり、企業によって金額は異なります。
裁量権の大きさ
就業先にもよりますが、インターンはマニュアルどおりに業務をこなすだけではなく、「成果を出す」ための行動を求められることがあります。そのため、アルバイトよりも裁量権があったり、専門スキルの習得が可能になったりもします。インターンは専門的な職種から総合職まで幅広く募集があるので、アルバイトでは募集されないような職種に挑戦できるチャンスがあるでしょう。
シフトの柔軟性
インターンシップはそもそも大学生・大学院生を対象としているので、授業や部活と両立できるようなスケジュールを組んでくれる企業がほとんどです。インターンシップ先の企業によって勤務日数や出勤時間が異なり、自由度が高いところもあれば、フルタイムでの勤務を求められるところもあります。長期インターンシップは特に忙しそうに見えますが、参加している学生のほとんどが大学生活と両立しているので安心してください。
3. インターンシップの職業例8選

では、インターンシップにはどのような職種があるのでしょうか。インターンシップの職業例について解説します。
1.セールス(営業)
セールス(営業)は社会人としての経験値を高めるのに適した職種です。具体的には、新規契約の獲得を目指し、アポイントを取ったり、商品やサービスをクライアントに提案したりします。名刺交換や企業への電話のかけ方、ビジネスメールの書き方など、基本的なビジネスマナーはひととおり学ぶことができるでしょう。お客さまの要望を引き出すヒアリングスキルや、プレゼン資料の作成スキルも身に付きます。
2.マーケター(マーケティング)
マーケター(マーケティング)の仕事内容は、自社の商品やサービスをユーザーに利用してもらうための戦略設計、数値分析、改善施策の立案です。インターンシップでは主に、自社サービスの分析やSEO(検索エンジン最適化)対策、メディア内のコンテンツの充実化、競合の調査などの業務が多いようです。分析力が身に付くうえに、マーケティングに必要な論理的思考を習得することができるでしょう。
3.プランナー(企画)
プランナー(企画)のインターンシップの仕事内容は企業によってさまざまですが、主に商品企画や営業企画、宣伝、広告、広報やPR、新サービスの立ち上げなどです。企業によってマーケティングに近い仕事もあれば、営業に近い仕事もあります。特にベンチャー企業では、インターン生と一緒に新サービスや新規事業立ち上げに取り組むこともあります。
4.コンサルタント(コンサルティング)
コンサルタントの仕事は、事業の分析や考察、クライアントが現状抱える問題の把握、それに対する解決案の作成や提案です。コンサルタントのインターンシップでは、クライアントが抱える問題を解決するために必要な調査をしたり、資料を作成したり、施策を立案したりします。これらを経験することにより、リサーチ力や資料作成力が身に付き、論理的思考などを学ぶことができるでしょう。
5.エンジニア
エンジニアのインターンシップでは、プログラミング言語を用いてさまざまなWebアプリケーションの開発に取り組みます。自社サービスの設計や開発、テスト、不具合の修正などを行うこともあれば、他社サービスの受託開発に関わることも。専門知識が求められることに懸念を感じる人もいるかもしれませんが、プログラミングを学んだことがない学生でも参加できるインターンシップもあります。
6.Webデザイナー
Webデザイナーのインターンシップでは、自社サービスのデザイン、Webサイトやスマホアプリのデザインなどを行います。専門的なツールを使った画像加工やデザイン、プログラミング言語を使ったコーディングも業務の一部です。将来デザイナーとして活躍したい方はもちろん、Webデザインに興味がある人や、コーディングスキルを磨きたいという学生にもおすすめです。作品制作の実績をポートフォリオとして残せるのもメリットの一つです。
7.編集者・ライター
編集者・ライターのインターンシップでは、書籍や雑誌、Webメディア、アプリなどのコンテンツを制作します。具体的な業務は、記事の執筆や編集、校正、翻訳などです。場合によっては取材や撮影を担当することも。相手に分かりやすく伝える文章力は汎用性の高いスキルなので、習得しておいて損はないでしょう。
8.接客スタッフ
接客スタッフのインターンシップでは、ホテルや百貨店などでの接客を担当します。長期インターンシップでは、販売促進の戦略や企画を考えるといった業務を任せてもらえることも。キャンペーンやクーポン・割引きなどの顧客向けサービスを考えたり、店頭のPOPを作ったりすることも業務の一つです。社会人としてのビジネスマナーやコミュニケーション能力も身に付くでしょう。
4. 将来を考えるきっかけになるのがインターンシップ

大学1・2年生(1,022名)を対象にした「マイナビ 大学生低学年のキャリア意識調査(26・27年卒対象)」によると、アンケートに回答した学生の約6割が「大学卒業後に就きたい仕事・キャリアの方向性が定まっていない」と回答しています。つまり、大学1・2年生の段階で自分の進路を決めきれていないのは一般的なことだと言えそうです。
キャリアの方向性を定めきれない理由については、約半数の学生が「『これだ』というものに出会えていないから」と回答しました。インターンシップを経験することは、そんな人たちの参考にもなるでしょう。実際に仕事を体験することで、進路を取捨選択しやすくなるかもしれません。
5. インターンシップに参加するメリット

ここではインターンシップに参加するメリットについて解説します。
自分の特性や強みが理解できる
インターンシップは自分を見つめ直す絶好の機会。自分は何が好きなのか、何が得意なのか、将来どういうことをしたいのかを考えるきっかけになります。それらが明確に見えてくれば、これからの学生生活ですべきことも見えてくるでしょう。また、実際に仕事を体験することによって「社風」や「仕事内容」とはどういうものかを間近で実感できるようになるので、就活時に求人を見る目が養われるでしょう。
自分のスキルを高めることができる
インターンシップは、就業体験を通して新たな知識やスキルも得ることができます。アルバイトでは任されないような専門的な業務や責任ある業務を体験することで、多くのことを学べるでしょう。先輩社員たちや他のインターン生など、普段の大学生活では出会えない人たちとも多く出会えるので、学ぶことも多いはずです。
「ガクチカ」としての経験が積める
インターンシップの参加経験があると、就職活動の面接で「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」を問われたとき、インターン先での経験を答えることができます。ただし、単に参加すれば良いということではなく、自分なりに参加する目的を明確にしておきましょう。そこで学んだこと、成果を挙げたこと、問題にぶつかったときにどう乗り越えたかがガクチカとして注目されるためです。
社会人との繋がりができる
インターンシップに参加すると、企業で働く社会人の方々と接することになります。普段は同世代としか出会う機会がない人も、企業で働く社員の姿を間近で見ることで、将来のキャリアやビジョンを描きやすくなることもあります。また、社会人だけではなく他のインターン生ともつながりができ、人脈が広がる可能性もあります。
企業に自分を知ってもらえる
企業側は、インターンシップで得た学生情報を採用選考活動に使用することができます(一定の基準を満たしたインターンシップに限る)。そのため、学生にとっては志望する企業に自分をアピールするチャンスです。進みたい業界や企業がある人は、インターンシップで活躍し、自分の存在を志望する企業に知ってもらいましょう。
本選考の予行練習にも最適
インターンシップの選考フローは、以下の流れが一般的です。
- ES(エントリーシート)の提出
- 面接(1回〜2回)
- インターンシップへの参加
これは就活の選考フローともよく似ています。選考のあるインターンシップを選べば、ESを書くことや面接に慣れることができるかもしれません。インターンシップの選考で、就活の予行演習をしておきましょう。
6. インターンシップのデメリット
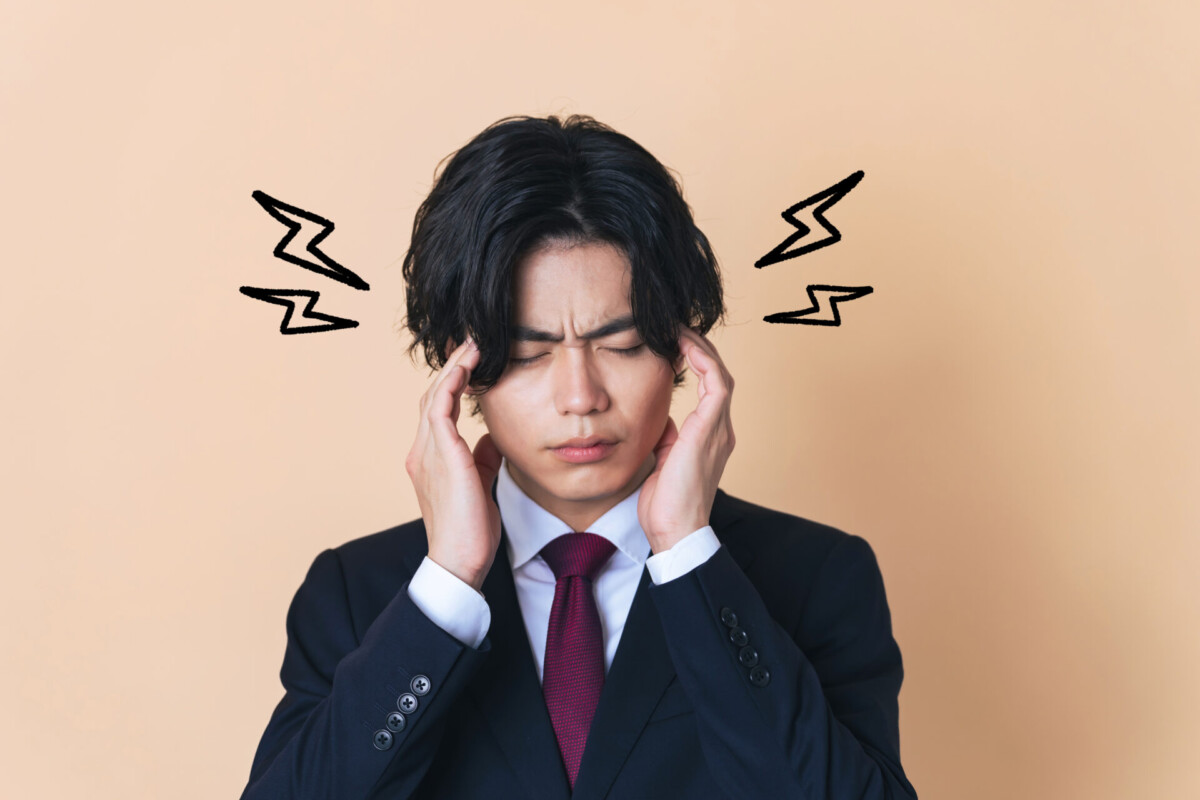
スキルアップや社会経験を得られるなどのメリットが多いインターンシップですが、中にはデメリットを感じる人もいます。では、インターンシップにはどのようなデメリットがあるのでしょうか。
学業との両立が難しい場合がある
ほとんどのインターン先企業では学業との両立ができるよう勤務時間などを配慮してくれますが、人によってはキャパオーバーになってしまうことも。インターンシップによって学業をおろそかにしてしまっては本末転倒なので、自分の体力や自由に使える時間を考慮し、計画的にスケジュールを調整しましょう。
内定がもらえるとは限らない
企業側は、インターンシップで得た学生情報を採用選考活動に使用することができますが、あくまでもインターンシップは就業体験の場。学生は、インターンシップに参加したからといって、必ずしも本選考で内定がもらえるとは限りません。基本的には「インターンシップと採用選考活動は別物」と考えましょう。
7. インターンシップの応募期間

インターンシップへの参加タイミングとしては、特に6月頃から始まる「サマーインターンシップ」や、10月頃から始まる「秋冬インターンシップ」など、長期休暇に重なる時期に行われるものが狙い目です。
インターンシップの申し込みを受け付ける時期は企業によって異なりますが、開催の3カ月前を目安に告知や申し込みが行われることが多いようです。時期を見逃さないように前もって募集情報をチェックしておきましょう。
8. インターンシップの探し方

インターンシップに興味がある場合、どうやって企業を探せばいいのでしょうか。インターン先の探し方について解説します。
大学のキャリアセンターに相談する
大学のキャリアセンターや就職課に相談すれば、インターンシップ先を紹介してもらえるうえ、ESの作成や面接対策などのサポートを受けられることもあります。
キャリアセンターを通せば、学校からの推薦を受けなければ応募できない「大学推薦型のインターン」に応募することも可能です。官公庁や地方公共団体、一部の大企業が大学推薦型のインターン方式を取っていて、希望者が多い場合は大学にて選考を行い、インターンシップ参加者を選抜します。また、OB、OGからインターン先を紹介してもらうのも一つの手でしょう。
インターンシップ紹介サイトを利用する
インターン先を手早く探すなら、インターネットがおすすめです。企業の採用ページや、インターンシップ・就職情報をまとめたサイトやアプリをこまめにチェックすると良いでしょう。特定の業界に特化したもの、ベンチャー企業を中心としたものなど、サイトによって特徴が違うので、目的に合ったサイトを選びましょう。
9. まとめ
インターンシップに参加することは、キャリア形成や実務について学べるだけでなく、自分の適性や強みについて理解を深めるための機会にもなります。また、普段の大学とは違った環境に身を置くこと自体も良い経験となることでしょう。このようにインターンシップは想像以上に多くのものを得られる可能性があるものです。気になる企業のインターンシップがあれば応募期間を逃さないよう、早めに調べて応募してみましょう!